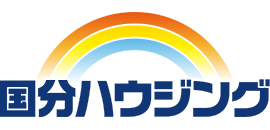Blog / Column
スタッフブログ・コラム
家づくりコラム
土地探しについて
2022.11.08
建ぺい率と容積率とは?基本知識から計算方法、緩和条件について

夢のマイホームを計画する時間は人生でも最も希望に満ちた瞬間ともいえます。
しかし、住宅作りは何もかもが自由自在というわけにもいかず、さまざまな制限を守らなくてはなりません。
初めて家を取得する方ほど「建ぺい率」と「容積率」については知っておくことは重要です。
今回は、新たな住まいを建てる際に知っておきたい建ぺい率と容積率について解説します。
ここでは建ぺい率と容積率とは何を意味するのかという基礎知識から、計算方法、緩和条件まで説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
建ぺい率とは
建ぺい率とは「土地面積と建築された建物面積の割合」のことをいいます。
例えば、土地面積が100m2で建物面積が50m2の場合、建ぺい率は50%となります。
建ぺい率は行政により上限が決められており、該当の土地に対して建ぺい率の上限を超える建物は建築できない決まりです。
仮に建ぺい率が50%と決められている用途地域の場合、100m2の土地に対して50m2の建物しか建てられないわけです。
建ぺい率は用途地域と呼ばれる区分により決められており、最低で30%から最高で80%までの幅があります。
一般的な住宅の場合はどの地域も建ぺい率60%までとされていることが多いですが、自分が居住する地域ごとにも違うので事前に確認しておくのがおすすめです。
容積率とは
容積率とは「土地面積と建物の延べ床面積の割合」のことをいいます。
例えば、土地面積が100m2で建物の延べ床面積が60m2(1階の延べ床面積)と50m2(2階の延べ床面積)だった場合、容積率は両者を合算して110%となります。
容積率も行政により上限が決められており、該当の土地に対して容積率の上限を超える建物は建築できない決まりです。
仮に容積率が110%と決められている用途地域の場合、100m2の土地に対して110m2の延べ床面積の建物しか建てられないのです。
容積率も用途地域と呼ばれる区分により決められており、最低で50%から最高で1,000%までの幅があります。
一般的な住宅の場合はどの地域も容積率200%までとされていることが少なくありませんが、自分が居住する地域ごとにも異なるので事前に確認しておくのがおすすめです。
用途地域と建ぺい率と容積率の関係
建ぺい率と容積率を考える上で欠かせないものが「用途地域」です。
用途地域は計画的な市街地を形成するため、用途に応じて13地域に分けられたエリアのことを指します。
用途地域を守らずに誰もが好き勝手に土地を購入して建物を建築してしまうと都市開発もままなりません。
それを防ぐための決まりが用途地域です。以下、用途地域の13区分となります。
| 用途地域 | 用途内容 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅専用(高さ10~12mほど) | 30・40・50・60% | 50・60・80・100・150・200% |
| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅専用(小型店舗含む) | 30・40・50・60% | 50・60・80・100・150・200% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅専用 | 30・40・50・60% | 100・150・200・300% |
| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅専用(店舗・事務所含む) | 30・40・50・60% | 100・150・200・300% |
| 第一種住居地域 | 住宅(小型店舗含む) | 60% | 200・300・400% |
| 第二種住居地域 | 住宅(店舗・事務所含まない) | 60% | 200・300・400% |
| 田園住居地域 | 住宅(農業の利便性を重視) | 30・40・50・60% | 50・60・80・100・150・200% |
| 準住居地域 | 住宅(道路や自動車関連施設の利便性を重視) | 60% | 200・300・400% |
| 近隣商業地域 | 商業施設(近隣住民の利便性を重視) | 80% | 200・300・400% |
| 商業地域 | ほぼすべての種類の建物(大型工場は含まない) | 80% | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000% |
| 準工業地域 | 工業施設(住宅や小型店舗含む) | 60% | 200・300・400% |
| 工業地域 | 工業施設(環境破壊の出る工場含む) | 60% | 200・300・400% |
| 工業専用地域 | 工業施設(住宅含まない) | 30・40・50・60% | 200・300・400% |
家を建てる方は以上の用途地域を事前に確認しておかなければなりません。
ただ、用途地域には商業地域や工業地域が含まれているものの、一般的な住宅の場合は関係ありません。
通常の住宅は住宅地域に設定されている用途内容となるため、その範囲の建ぺい率と容積率を確認しておけば大丈夫です。
建ぺい率・容積率の調べ方
建ぺい率と容積率の調べ方には主に2つの方法があります。
- 市区町村役場の建築指導課または都市計画課に問い合わせる
- 不動産業者や建設業者(工務店・ハウスメーカー)に問い合わせる
建ぺい率や容積率を調べる最も確実な方法としては市区町村役場の建築指導課や都市計画課に問い合わせる方法があります。
この方法であれば地域ごとに設定されている建ぺい率と容積率を確認できます。
詳しく知りたい場合は、役所の職員に確認するとより安心です。
また、土地を購入する際に不動産業者に聞いたり建物を建築する際に建設業者に聞いたりするのもおすすめです。
不動産のプロであれば用途地域に関しては把握していますし、工務店やハウスメーカーも必ず把握しています。
そのほか、特定行政庁から建築主へ通知される建築確認通知書や特定行政庁の窓口で確認できる建築計画概要書に目を通しておくのも良いでしょう。
併せて、前述した用途地域一覧表に目を通すことで、おおよその建ぺい率・容積率も確認できます。
建ぺい率・容積率の計算方法
ここからは建ぺい率・容積率の計算方法についてご紹介します。
まずは建ぺい率・容積率の計算式を確認しておきましょう。
| 建ぺい率の計算方法 | 建物面積÷土地面積×100 |
| 容積率の計算方法 | 延べ床面積÷土地面積×100 |
建ぺい率・容積率と聞くと難しく聞こえますが、それぞれの数字を当てはめるだけで簡単に計算できます。
例えば「土地面積100m2で建物面積50m2(1階部分)+40m2(2階部分)」だった場合、建ぺい率・容積率の計算式は以下の通りです。
・建ぺい率=50m2÷100m2×100=50%
・容積率=90m2÷100m2=90%
基本的に建ぺい率の計算では物件を真上から見た面積を使用し、2階建ての物件であれば1階部分と2階部分の広い方から計算する決まりとなっています。
その一方で容積率の計算では1階部分と2階部分の延べ床面積を合算して計算する決まりとなっています。
ここが建ぺい率と容積率の計算方法における相違点となるので注意しましょう。
ただし、建ぺい率は関係ないものの容積率においては「前面道路制限」があります。
これは「敷地に面する道路の幅が12m未満の場合、その幅員に定数を掛けて算出した数字の小さい方が上限となる」という制限となります。
仮に容積率が200%でも4mの道路に接していて定数が0.4の場合、上限が160%まで制限されてしまうということです。
建ぺい率・容積率に関する注意点
「ちょっとくらいならはみ出しても…」と思うかもしれませんが、制限を破ると大変な目に遭います。
ここからは建ぺい率と容積率を考える上で知っておきたい注意点について見ていきましょう。
違法建築物扱いとなってしまう
建ぺい率と容積率は土地や建物だけでなく、街並みを守るために設定されています。
そのため、制限を守らない物件に関しては違法建築物扱いとなるという点には注意しましょう。
日本では建ぺい率と容積率の他にもいくつかの制限が設けられています。
例えば、以下がその代表的なものとなります。
- 絶対高さ制限
- 高度地区制限
- 斜陽制限
- 日陰制限
以上の制限も細かな内容が設けられており、制限を破った物件は違法建築物として扱われてしまいます。
地域によっては独自の制限を設けている場合もあるため、自分が居住する予定の地域にはどのような制限があるのかを必ず確認しておきましょう。
工事を断られてしまう
建ぺい率と容積率を守らない場合は工事自体が断られてしまうこともあります。
工務店やハウスメーカーはあくまでも建築基準法に則った家しか作れません。
オーナーとなる方がいかに詳細な要望を熱弁しても、それが制限を超えるものであれば契約はできません。
住宅ローンが組めない
建ぺい率と容積率をオーバーする物件は違法建築物となるため、金融機関も融資を行えません。
住宅ローンは物件を担保として融資を行うのが基本ですが、違法建築物は担保としての価値もない状態です。
そのため、制限を守らない家は住宅ローンが組めないという点にも注意しておきたいです。
建ぺい率・容積率を守って広い家を建てるポイント
ここまで建ぺい率や容積率について知ると「制限ばかりで理想の家を建てられそうもない」と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、建ぺい率や容積率には緩和条件というものが設定されています。
緩和条件さえクリアすれば同じ建ぺい率・容積率でも広い家を建てられるので、ぜひ緩和条件をうまく活用しましょう。
地下室
地下室を作る場合、物件全体の1/3以内であれば建ぺい率・容積率の計算に含めなくても良いという緩和条件があります。
例えば、100m2の物件であれば全体の1/3に相当する約30m2までの地下室が問題なく作れるということです。
バルコニー・ベランダ
バルコニー・ベランダを作る場合、外壁から突き出した部分が1m以内であれば建ぺい率・容積率の計算に含めなくても良いという緩和条件もあります。
同様に庇や出窓も計算に含めなくて構わないので、同じ建ぺい率・容積率を保ちながら部屋を広くできます。
ただ、庇や出窓は細かい条件もあるので注意してください。
- 床面から出窓の端まで30cm以上の高さがあること
- 外壁から50cm以上突き出ていないこと
- 出窓部分の1/2以上が窓であること
ロフト・屋根裏
ロフト・屋根裏を作る場合、該当フロアの床面積に対して1/2以内であれば建ぺい率・容積率の計算に含めなくて良いという緩和条件もあります。
あくまでも該当フロアの床面積に対して半分までという条件付きですが、有効活用すれば限られた建ぺい率・容積率でも部屋を増やせます。
ただし、他にも細かな条件があるだけでなく制限を超えてしまうと1階層分が増えることになってしまうので、空間のサイズには注意しましょう。
吹き抜け
吹き抜けは天井から地面まで突き抜けているため、床がないものとしてみなされます。
そのため、吹き抜け部分は床面積として算入されません。
吹き抜けと階段が隣接している場合は階段部分も床面積として算入されないため、工夫次第でかなりのスペースを確保できます。
ガレージ・車庫
ガレージ・車庫を作る場合、1/5以内であれば建ぺい率・容積率に不算入となります。
ガレージや車庫をうまく物件に取り入れれば居住部分を広く保ちつつ、ほかの空間も確保できるので、倉庫としても兼用できて便利です。
まとめ
建ぺい率と容積率は家を建てる際に欠かせない要素となります。
両者の制限を守らないと違法建築物扱いとなり、弊害も出てきてしまいます。
そのため、必ず居住する地域の建ぺい率と容積率は確認しておかねばなりません。
この記事では、基礎知識から計算方法、緩和条件までをまとめてご紹介しました。
国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。
・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない…
・マイホームに必要な資金って具体的にいくら?
・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要?
・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能?
といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。
国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から!