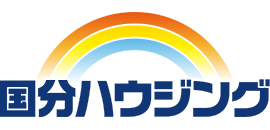Blog / Column
スタッフブログ・コラム
家づくりコラム
資金(ローン)について
2023.03.30
住宅ローン控除(減税)とは?計算方法や適用条件・申請方法を徹底解説
!受ける条件や流れは?.jpg)
家を購入する際の住宅ローン控除(減税)を利用する際には、どのような制度なのかを正確に把握しておく必要があります。
また、購入する不動産によって適用条件や控除額が変わるため、家づくり全体の総額にも影響がでてしまうポイントといえます。
この記事では、住宅ローン控除(減税)の計算方法や適用条件、申請方法について解説していくので、現在家の購入を検討している人は、是非最後までお読みください。
| 【この記事でわかること】
● 住宅ローン控除(減税)の概要 ● 住宅ローン控除(減税)の計算方法 ● 住宅ローン控除(減税)の適用条件 ● 住宅ローン控除(減税)の申請方法 |
住宅ローン控除(減税)とは?
住宅ローン控除(減税)とは、国税庁が公開している減税措置で、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
住宅購入の促進を目的とした制度で、1972年に導入された「住宅取得控除」からはじまり数回の改正を経て現在の制度に至ります。
住宅ローンを利用することで、年末の残債に応じて所得税と住民税が控除される制度であり、家を購入する人であれば利用する価値が高い減税措置といえます。
令和4年以降の住宅ローン控除(減税)はどのように改正された?
前述したように住宅ローン控除(減税)は何回か改正しており、令和4年以降の内容が最新となります。ここでは、令和4年度に改正された内容を解説します。
- 控除期間が10年から13年になる
- 控除率が1%から0.7%になる
- 制度自体が2025年まで延長される
- 住宅の性能や時期によって借入限度額が変動する
順番に見ていきましょう。
控除期間が10年から13年になる
消費税10%に対する特別措置として、2019年度から控除期間が10年から13年に延長となっていますが、令和4年以降においても同様の措置が適用されます。
ただし、リフォームされていない中古住宅や新築住宅でない場合は10年となるため、注意が必要です。
控除率が1%から0.7%になる
令和4年度より、控除率はこれまでの1%から0.7%に引き下げられます。
これは、長く続く低金利政策により住宅ローンの支払い額が下がり、実質住宅ローン支払い額に対し住宅ローン控除(減税)の控除額が多くなってしまう背景があるからです。
こういった逆転現象を解消するために、控除率が調整されました。
制度自体が2025年まで延長される
2022年を区切りとしていた住宅ローン控除(減税)ですが、令和4年の税制改正の大綱をもって、2025年まで延長されることになりました。
住宅の性能や時期によって借入限度額が変動する
住宅ローン控除(減税)は全ての不動産や購入者、居住タイミングに適用するわけではありません。
たとえば、通常の新築住宅では3,000万円、中古住宅であれば2,000万円が借入残高の上限となります。ただし、長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けている場合は新築住宅で4,500万円、中古住宅で3,000万円となります。
また、住宅ローンを組む人の所得が2,000万円以下であることや、家が完成してから半年以内に入居するといった条件もあります。
このように、住宅ローン控除(減税)を利用するためには確認する項目がいくつかあることを知っておきましょう。
住宅ローン控除(減税)の計算方法
住宅ローン控除(減税)の計算方法は、以下の通りです。
| 年末時点の住宅ローン残高×控除率(0.7%)×控除期間(10年or13年) |
また、控除の上限は購入する不動産によって定められているため、それぞれの上限額を確認しましょう。
住宅ローン控除の上限額
住宅ローン控除の上限額は、以下の通りです。
| 長期優良住宅 | 低炭素認定住宅 | ZEH住宅 | 省エネ住宅 | その他 | |
| 新築住宅 | 4,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 中古住宅 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 |
新築住宅の場合、長期優良住宅と低炭素認定住宅であれば4,500万円が上限額となりますが、ZEH住宅と省エネ住宅は、それぞれ3,500万円と3,000万円です。
それ以外であっても、令和5年以内に建築確認を取得した住宅であれば3,000万円が上限となりますが、令和6年以降は適用外となるため注意が必要です。
また、中古住宅は性能住宅であれば全て3,000万円となり、それ以外は2,000万円が上限額になります。
住宅ローン控除(減税)の適用条件
住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためにはいくつか条件があり、購入する不動産によって変化します。
- 新築住宅の場合の適用条件
- 中古住宅の場合の適用条件
- 増築やリフォームの場合の適用条件
ここでは、上記3点の適用条件を解説します。
新築住宅の場合の適用条件
新築住宅の適用条件は次のようになります。
- 完成もしくは購入後6ヶ月以内に居住すること
- 控除を受ける12月31日まで居住していること
- 住宅面積が50㎡以上あり、さらに床面積の1/2を住宅用として利用していること
- 控除を受ける人の所得が2,000万円以下であること
- 住宅ローンの借入期間が10年を超えること
- 控除を受ける年の3年以内に、譲渡所得の課税特例を受けていないこと
- 贈与や親族間の売買でないこと
住宅ローン控除(減税)は、あくまでも居住用物件の購入促進を目的としているため、控除を受ける人が住んでいることが条件です。
また、住宅ローン控除(減税)を受けるために購入し短期間で売却することを防ぐという意味で、10年以上の住宅ローン借入や譲渡所得の課税特例について制限がかけられています。
そのため、新築住宅の場合は住む目的で購入するのであれば問題なく条件をクリアできます。
中古住宅の場合の適用条件
中古住宅の適用条件は、以下の通りです。
- 完成もしくは購入後6ヶ月以内に居住すること
- 控除を受ける12月31日まで居住していること
- 住宅面積が50㎡以上あり、さらに床面積の1/2を住宅用として利用していること
- 控除を受ける人の所得が3,000万円以下であること
- 住宅ローンの借入期間が10年を超えること
- 控除を受ける年の3年以内に、譲渡所得の課税特例を受けていないこと
- 贈与や親族間の売買でないこと
- 建築後に使用された中古住宅であること
- 築年数が20年以内、耐火建造物では25年以内であること
- 耐震基準に適合した建物であること
中古住宅の場合は新築住宅の適用条件に加え、1度でも使用されている建物であることや築年数の制限、耐震基準適合を取得しているなどの条件が追加されます。
そのため、全ての条件をクリアしているかどうかは、事前に不動産会社に確認することをおすすめします。
増築やリフォームの場合の適用条件
増築やリフォームの場合、中古住宅の要件に対して以下が追加となります。
- 完成もしくは購入後6ヶ月以内に居住すること
- 控除を受ける12月31日まで居住していること
- 控除を受ける人が住むための増築やリフォームであること
- 増築やリフォームにかかる費用が100万円を超えており、1/2以上が居住用部分の工事であること
- 増築やリフォームが次の内容であること
- 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替えの工事
- マンションの場合床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- 居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関床、壁のすべてについて行う修繕・模様替えの工事
- 耐震工事、バリアフリー工事、省エネ改修工事
増築やリフォームにおいても住宅ローン控除(減税)を利用できますが、控除を受ける人が住むための家に限定されます。
また、工事の内容についても制限があるため、あらかじめ確認することが重要です。
住宅ローン控除(減税)の申請方法
この章では、住宅ローン控除(減税)の申請方法を解説します。
- 初年度は確定申告する
- 2年目以降は年末調整する
- 手続きを忘れた場合は5年以内に還付申告する
順番に見ていきましょう。
初年度は確定申告する
住宅ローン控除(減税)は、初年度のみ確定申告が必要となります。
このタイミングで初めて確定申告する人も多いため、e-taxなどの簡潔に実施できるツールを選ぶことが重要です。
2年目以降は年末調整する
初年度に確定申告すると、2年目以降は年末調整で控除額を還付できるようになります。
そのため、年末調整を忘れずに実施することを覚えておきましょう。
手続きを忘れた場合は5年以内に還付申告する
住宅ローン控除の申請を万が一忘れてしまっても、5年以内であれば還付申告が可能です。
ただし、その場合は借入した年から遡って確定申告する必要があるため、注意しましょう。
住宅ローン控除(減税)の注意点
住宅ローン控除(減税)は便利な点が多いですが、注意点もあります。
- 住み替え時には利用できないケースがある
- 住宅ローンの借り方によっては控除額が大きく減るケースがある
- 住宅ローンの返済方法によっては控除額が大きく減るケースがある
順番に見ていきましょう。
住み替え時には利用できないケースがある
家を売却し、新しく家を購入する際に譲渡所得に関連する税制優遇を受けている場合、売却から購入までの期間が3年以内であれば住宅ローン控除(減税)を利用できません。
そのため、売却するタイミングでどちらの税制優遇を利用するのが得なのか検討する必要があります。
住宅ローンの借り方によっては控除額が大きく減るケースがある
住宅ローンを夫婦で借りる場合、収入合算で借入した場合は主債務者のみが控除を受けられます。そのため、夫婦の年収によっては最大額まで控除を受けられないこともあります。
住宅ローンの返済方法によっては控除額が大きく減るケースがある
住宅ローンを組み、繰り上げ返済を繰り返していくと、ローン残債の減少が早くなります。
しかし、その場合は住宅ローン控除(減税)の控除額が繰り上げ返済しない場合に比べ大きく減ってしまいます。そのため、繰り上げ返済する場合においてもタイミングが重要です。
住宅ローン控除(減税)を実際にシミュレーション
ここでは、住宅ローン控除(減税)の控除額をシミュレーションしました。
なお、シミュレーションでは以下の条件を設定しています。
| 【条件】
● 借入額:5,000万円 ● 固定金利:1% ● 借入期間:35年 ● 年収:700万円 ● 借入開始:2023年3月 |
| 借入期間 | 認定新築住宅 | 新築住宅 | 認定中古住宅 | 中古住宅 |
| 初年度 | 49.0万円 | 40.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 2年目 | 47.8万円 | 40.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 3年目 | 46.6万円 | 40.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 4年目 | 45.3万円 | 40.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 5年目 | 44.1万円 | 40.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 6年目 | 42.8万円 | 40.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 7年目 | 41.6万円 | 40.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 8年目 | 40.3万円 | 40.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 9年目 | 39.0万円 | 39.0万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 10年目 | 37.7万円 | 37.7万円 | 20.0万円 | 20.0万円 |
| 11年目 | 33.3万円 | 26.7万円 | 13.3万円 | 13.3万円 |
| 12年目 | 33.3万円 | 26.7万円 | 13.3万円 | 13.3万円 |
| 13年目 | 33.3万円 | 26.7万円 | 13.3万円 | 13.3万円 |
| 控除額合計 | 約534万円 | 約477万円 | 約240万円 | 約240万円 |
※参考:住宅ローン控除(減税)シミュレーション|不動産・マンション売却のオウチーノ
年収700万円の人が5,000万円の住宅ローンを借入した場合、中古住宅と新築住宅では控除額に約200万円の差があることがわかりました。
住宅ローン控除(減税)に関するよくある質問
この章では、住宅ローン控除(減税)に関するよくある質問を紹介します。
- 住宅ローン控除はいつまでに申請する?
- 住宅ローン控除の年末調整で必要な書類は?
- 住宅ローン控除の還付金はいつ受け取れる?
順番に回答していきます。
住宅ローン控除はいつまでに申請する?
住宅ローン控除は住宅ローンの支払いが開始された年の翌年に、確定申告にて申請します。
ただし、忘れた場合でも5年以内であれば申告可能です。
住宅ローン控除の年末調整で必要な書類は?
年末調整では「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類や、住宅ローンの年末残高が分かる書類が必要です。
計算明細書は、初年度の確定申告時に13年分まとめてもらうため、紛失しないように注意しましょう。
住宅ローン控除の還付金はいつ受け取れる?
住宅ローン控除の還付金は企業によって異なりますが、主に翌年の2~3月が一般的です。
住宅ローン控除(減税)は改正後の内容に注意しよう
住宅ローン控除(減税)は非常に便利な制度ですが、法改正により控除率や限度額の変更などがあり、正しい情報による判断が重要です。
国分ハウジングでは、家づくりのプランだけではなく住宅ローンなどの資金面においても相談を承ります。住宅ローンについてお悩みの方も、ぜひ一度国分ハウジングまでご相談ください。