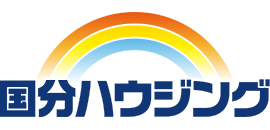Blog / Column
スタッフブログ・コラム
家づくりコラム
資金(ローン)について
2023.01.27
不動産取得税の計算方法とは?特例や軽減措置、かからないケースも解説

家の購入を検討する際には、不動産取得税が発生します。
消費税や車の重量税とは違い、不動産の取得時にしか支払う義務が生じないため、馴染みがない税金です。しかし、家を買う前に不動産取得税について理解しておく必要があります。
そこで、この記事では不動産取得税の特徴や計算方法などを解説します。家の購入を検討している人は、ぜひ最後までお読みください。
| 【この記事でわかること】
● 不動産取得税の特徴 ● 不動産取得税の計算方法 ● 不動産取得税の軽減措置とかからないケース |
そもそも不動産取得税とは
不動産取得税とは都道府県に支払う税金で、不動産を取得した法人または個人が対象です。
相続以外の売買や贈与、遺贈により取得した場合に対象となり、土地や家屋など不動産の種類を問わず課税されます。
総務省のHPでは「取得」について定義されており、有償と無償に限らず不動産所有権を得た事実がある場合に取得と見なされます。
不動産取得税を支払うタイミング
不動産取得税は、所有権移転の通知が法務局から各都道府県に通達されると、その税額が計算されます。
税額の決定を受けて納税通知書が送付されるため、支払うタイミングは納税通知書が届いてからです。
早ければ3ヶ月前後、長い場合は1年以上かかるケースもあるものの、支払いが決定した場合には必ず通知書が発行されることを覚えておきましょう。
不動産取得税の計算方法
この章では不動産取得税の計算方法について解説します。不動産取得税は「固定資産税評価額×税率」で計算され、後述する優遇措置を加味する上で基準となる計算です。
- 不動産の評価額
- 不動産取得税の税率
上記の2つについて、順番に見ていきましょう。
不動産の評価額
不動産取得税の計算で使用される評価額は、固定資産税評価額と呼ばれます。
課税明細書の確認や固定資産課税台帳の閲覧申請、固定資産評価証明書を入手すると評価額の確認が可能です。
ただし、新しく購入した土地や建てた家にはまだ台帳記録がないため、都道府県からの納税通知書で確認する必要があります。
不動産取得税の税率
不動産取得税の税率は原則4%であり、土地と建物に対する軽減措置は、この税率を基準として期限付きで適用されます。
不動産取得税に利用できる特例や軽減措置
前述した不動産取得税の計算に対して、土地と建物それぞれに特例や軽減措置があります。
したがって、家を建てる際には特例や軽減措置が適用された不動産取得税になることを把握しましょう。なお、特例および軽減措置は、国土交通省および鹿児島県が公開している内容をもとに解説します。
これらは、令和6年3月31日までの不動産取得を期日とした特例および軽減措置となります。
- 新築住宅における課税標準の軽減
- 中古住宅における課税標準の軽減
- 税率の軽減措置
- 宅地税額控除
順番に確認していきます。
※参考1:認定長期優良住宅に対する税の特例
新築住宅における課税標準の軽減
国土交通省は住宅の流通コスト軽減を通じ、良質な住宅の建設および流通を促進するため、新築戸建ての取得時には課税標準から1,200万円を控除する特例措置を設けています。
また、取得する新築戸建てが認定長期優良住宅である場合、控除額が1,300万円となります。
そのため、取得する新築戸建てが認定長期優良住宅に該当するか確認しましょう。
ただし、この軽減措置を受けるためには以下の条件を満たすことが必要です。
| ● 都道府県の条例で定めた内容を申告すること
● 床面積が50㎡以上240㎡以下であること |
中古住宅における課税標準の軽減
中古住宅の取得においても課税標準の軽減はありますが、築年数によって控除額が変わります。
そのため、取得する物件の新築年月日を確認しましょう。
新築年月日と、それに対応する控除額は以下の通りです。
| 新築の時期 | 控除額 |
| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日(※) | 350万円 |
| 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日(※) | 420万円 |
| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
※建築士などから耐震基準に適合している旨が証明されている場合のみ適用(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了しているものに限る)
また、中古住宅の軽減措置においては以下の条件を満たす必要があります。
| ● 取得者個人がその住宅に居住するもの
● 床面積が50㎡以上240㎡以下であること ● 昭和57年1月1日以後に新築された、または建築士から耐震基準適合証明書などが発行されたもの |
税率の軽減措置
不動産を令和6年3月31日までに取得した場合、住宅建築用の土地と住宅であれば税率が4%から3%に軽減されます。
ただし、住宅以外の家屋については軽減対象外となるため注意が必要です。
宅地の税額控除
宅地は前述した税率の軽減措置と合わせ課税標準額が1/2となる特例を受けられ、さらに以下の軽減措置の対象になります。
なお、以下①と②のいずれかが高い方が控除額です。
| ①課税標準額に対し45,000円の控除
②土地の1㎡あたりの価格(※1)×住宅の床面積(※2)×2×3% |
※1:固定資産税評価額の1/2にあたる評価額を延べ床面積で除した価格
※2:限度面積200㎡
宅地の税額控除を受けるための条件は以下の通りです。
| ● 建築する建物が不動産取得税の軽減措置を受けること
● 土地を取得し不動産取得税の軽減措置を受けられる建物を建築するまで所有していること ● 不動産取得税の軽減措置を受けられる建物を建築し1年以内に土地を取得すること |
不動産取得税がかからないケース
不動産取得税は必ずかかるわけではなく、「免税点」と「非課税枠」に該当するケースであれば不動産取得税はかかりません。
そのため、この章で解説する2つのケースの確認をおすすめします。
- 課税対象にならない免税点
- 非課税枠
鹿児島県総務部税務課のHPを参考に、以下で解説します。
課税対象にならない免税点
課税対象にならない免税点は、主に以下の3点です。
- 取得した土地の価格が10万円未満の場合
- 建築(新築・増築・改築)した家屋の価格が23万円未満の場合
- 建築以外の原因(売買・贈与など)により取得した家屋の価格が12万円未満の場合
なお、免税点の価格においても購入価格ではなく、固定資産税評価額となります。
したがって、上記の免税点よりも高い価格で購入した場合であっても対象にならないケースがあるので、購入時には不動産会社に確認しましょう。
非課税枠
不動産取得税は、一部かからないケースがあり、以下の場合は非課税枠として扱われます。
- 相続取得した場合
- 法人の合併もしくは分割により取得した場合
- 公共の用に供する道路などを取得した場合
- 土地改良事業又は土地区画整理事業の施行に伴い換地を取得した場合
- 解体前提で建物を取得し、使用することなくただちに解体した場合
また、上記のケース以外にも非課税枠となるケースもあるため、不明な場合は不動産会社を経由して地域振興局や支庁に問い合わせをしましょう。
不動産取得税の計算を実際にシミュレーション
この章では、実際に不動産取得税をシミュレーションします。
将来発生する不動産取得税をイメージできるため、今後購入予定の物件と照らし合わせながら確認しましょう。なお、設計条件を以下に設定します。
| 【条件】
● 建物評価額:2,000万円 ● 土地評価額:800万円 ● 建物延べ床面積:100㎡ ● 土地面積:170㎡ ● 建物種類:新築 ● 取得時期:令和6年3月31日まで |
- 建物の不動産取得税額
- 土地の不動産取得税額
順番に見ていきましょう。
建物の不動産取得税額
建物の不動産取得税は、以下の計算式で算出できます。
| 建物の不動産取得税の計算式 | (評価額-控除額)×税率 |
つまり、長期優良住宅でなければ「(2,000万円-1,200万円)×3%=24万円」が不動産取得税となり、長期優良住宅であれば「(2,000万円-1,300万円)×3%=21万円」となります。
なお、住宅用の家屋でない場合は軽減措置がないため、「2,000万円×4%=80万円」が不動産取得税にあたります。
土地の不動産取得税額
土地の不動産取得税について、計算式は以下の通りです。
| 土地の不動産取得税の計算式 | 評価額×1/2×税率-軽減額 |
設計条件をあてはめた場合、「800万円×1/2×3%-14万円(※)」となり、マイナス約2万円であるため非課税となります。
| ※以下のうち高い方の軽減額を使用
①課税標準額に対し45,000円の控除 ②800万円×1/2×170㎡÷200㎡(※)×3%=約14万円 |
※100㎡×2=200㎡となるため、上限200㎡となる
不動産取得税の申告方法
この章では、不動産取得税を申告する方法や時期、納税方法について解説します。
- 申告の方法や時期
- 不動産取得税の納税方法
上記2点を順番に見ていきましょう。
申告の方法や時期
不動産取得税は、鹿児島県に不動産取得申告書(第75号様式)を提出すると申告できます。
また、申告時期は有償無償を問わず、取得の日から30日以内です。
不動産取得申告書の提出時には、マイナンバーの記載と本人確認が必要となるため、あらかじめ準備しましょう。
※参考:不動産取得申告書|鹿児島県
不動産取得税の納税方法
不動産取得税は、納税通知書が発行されるため通知書を使って納税します。したがって、事前にしっかりと用意しておき、いざというときに忘れないように注意しましょう。
不動産取得税の計算方法を押さえてしっかり準備しよう
不動産取得税は多くのケースが非課税となるものの、取得する建物の仕様や土地面積によっては課税対象になる場合もあります。
したがって、検討している土地と建物で不動産取得税がかかるか否かを事前に確認しましょう。
国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。
・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない…
・マイホームに必要な資金って具体的にいくら?
・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要?
・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能?
といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。
国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から!
https://kh-house.jp/event/