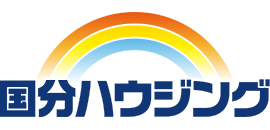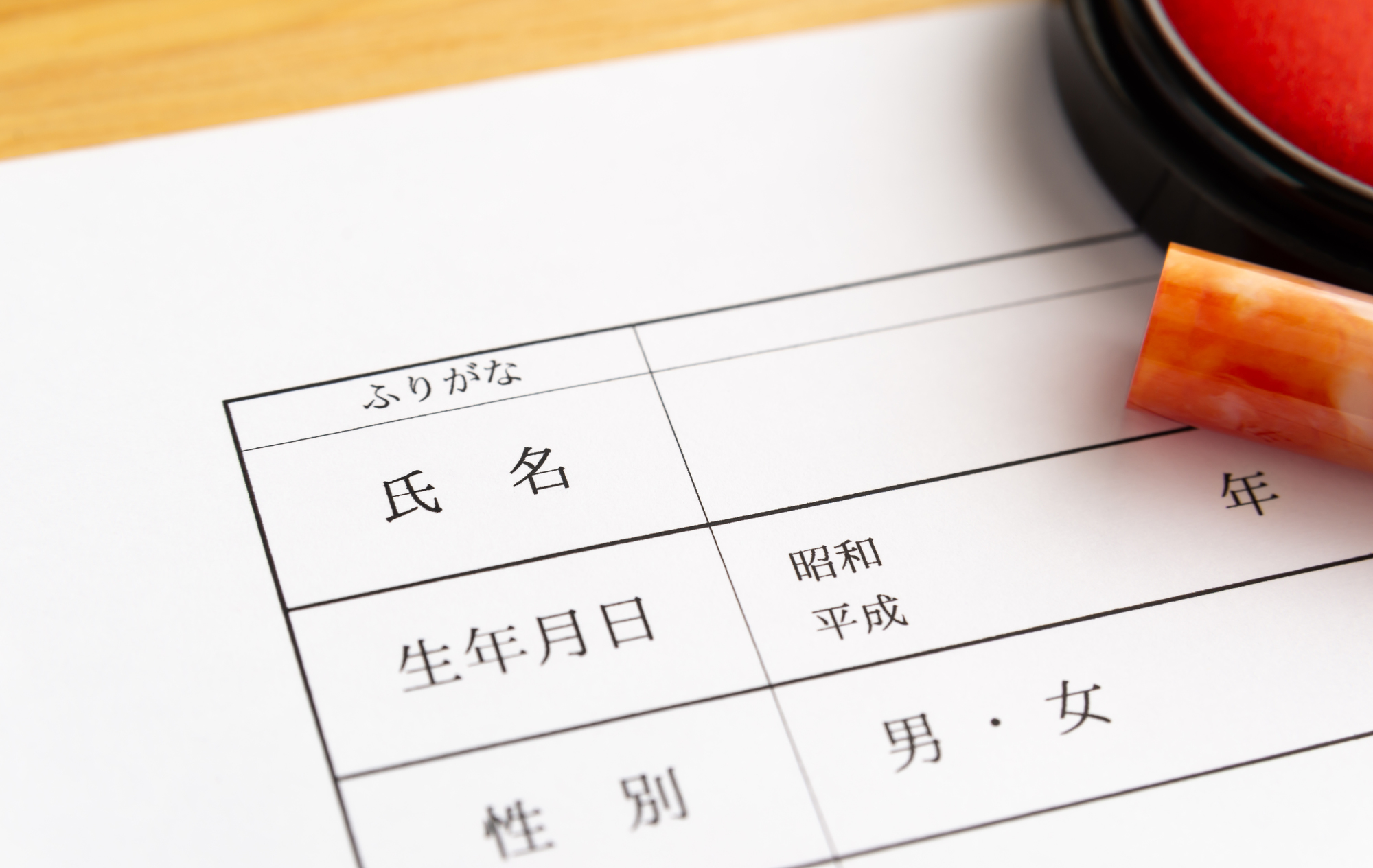Blog / Column
スタッフブログ・コラム
家づくりコラム
建物・家づくりについて
2022.11.30
家の寿命は何年?長く住み続けるコツや寿命が近づいた時の対処方法を解説

家は、経年劣化が進むことで寿命を迎えます。そのため、なるべく長く家を保持する方法を知っておくことで、安心して住み続けられる家が実現できるでしょう。
ここでは、家の寿命に関する考え方や長く安心して住むためのコツ、対処方法などについて解説します。家の寿命が心配な方は、ぜひ最後までお付き合いください。
| 【この記事でわかること】
● 家の寿命は様々 ● 家の寿命を伸ばす方法 ● 寿命を迎えた家の対処方法 |
家の寿命は何年?
家の寿命については住宅構造ごとによって変わりますが、一概に「何年経過したら必ず寿命を迎えて壊れる」というものではありません。また、家の寿命には耐用年数という考え方もあり、それぞれの違いについて知っておく必要があります。
- ・住宅構造ごとの寿命
- ・耐用年数との違い
ここでは、住宅構造ごとの寿命と耐用年数について、解説します。
住宅構造ごとの寿命
小松幸夫氏の「建物は何年もつか」によると、住宅構造ごとの寿命は以下の通りです。
- ・木造住宅:約54年
- ・鉄骨造:約52年
- ・鉄筋コンクリート造:約56年
上記の考え方は、実際に残存している建物の戸数を調べ、残存している確率が50%以下となる時点を寿命として設定しながら検証した結果です。
この結果から、住宅構造ごとに大きな差はなく50年以上の寿命があるとわかります。
耐用年数との違い
前述した考えとは異なり、日本には耐用年数という考え方もあります。耐用年数とは、建物が価値を保有できる期間を定めた指標で、会計上の減価償却などに使用されます。そのため、不動産取得を確定申告する人や自営業の人以外にとっては馴染みのない指標といえるでしょう。
耐用年数は国税庁のHPに各構造の耐用年数が公開されており、以下の通りとなります。
- ・木造住宅:22年
- ・鉄骨造:※27年(骨格材肉厚が3mmを超え4mm以下のもの)
- ・鉄筋コンクリート造:47年
※骨格材肉厚が4mmを超えるものは38年、3mm以下は19年
このように、耐用年数という考え方では木造と鉄骨造、鉄筋コンクリート造で大きな差があることがわかります。
これは、あくまで会計上の経費として算出できる減価償却という指標と、実際に利用できる家の状態が乖離していることが理由です。
つまり、家の寿命は使用する指標や家の状態によって大きく変わり、構造ごとに明確な寿命が定められているわけではないといえるでしょう。
海外の家よりも日本の住宅寿命が短い理由
海外の住宅は100年以上経過している建物が多くあり、重要文化遺産としてではなく、実際に居宅として有効活用されています。
したがって、日本の住宅は海外と比較した場合に寿命が非常に短いといえるでしょう。
- ・海外には地震が少なく、日本は地震が多い
- ・火災保険や地震保険によって補填する文化がある
ここでは、海外の家よりも日本の住宅寿命が短い理由について解説します。
海外には地震が少なく、日本は地震が多い
大きな理由の1つに、地震の数があります。
日本は、4つの大きなプレート上に国土があり、ヨーロッパやアメリカなどには見られない地震大国だといえます。そのため、海外の住宅は地震対策する必要がなく、レンガなどの耐久性がある建材が主に使用されており、100年以上経過しても問題なく住めます。
一方、地震が多い日本では地震対策が必須となるため、耐久性がレンガなどよりも劣る木造や鉄骨造の家が主流となります。
このように、地震が起きやすい日本では耐久性が高い家を建築できないという事情が、海外との寿命差に大きく関係しているといえるでしょう。
火災保険や地震保険によって補填する文化がある
火災保険は浸水や竜巻、台風における飛来物などの被害にも対応可能です。そのため、多くの人が家を購入するタイミングで加入し、万が一の住宅被害を保障する仕組みがあります。
また、日本には地震保険という制度があり、地震が発生し家で住めなくなった際に当面の生活費として充当されます。
このように、地震においても住宅の地震対策と地震保険によって、安全を確保するというのが日本の住宅環境だといえます。この方式は、ニュージーランドなど地震が多い国でも使われており、ハウスメーカーと国が住居者の安全を保障している仕組みです。
このように、日本では寿命が短い建材しか使えない分、火災保険や地震保険でカバーする仕組みによって安全な住環境が維持されています。
家の寿命を伸ばして長く住み続けるコツ3選
家の寿命を伸ばすためには定期的なメンテナンスが必要です。
- ・日常的な掃除
- ・設備の定期的な点検
- ・修繕や改修工事
ここでは、家の寿命を伸ばし長く快適に住むための方法について解説します。
日常的な掃除
掃除しないことで家屋内の環境が悪くなるだけではなく、それ以外にも家の寿命を縮めることにもなりかねません。
例えば、棚にホコリが積もっている状態で放置しているとダニやカビの温床になる可能性があります。コンセント付近にあるホコリは火災の原因にもなるため、こまめな掃除は非常に重要だといえるでしょう。
また、結露を拭かずに放置しておくと窓サッシ周辺の木部が腐食することにも繋がるため、注意しましょう。
日常的に掃除することで家の状態を視認でき、寿命を縮めるような原因の早期発見が可能です。このように、高い頻度で掃除することは、家の寿命を伸ばす上で非常に重要だといえるでしょう。
設備の定期的な点検
給湯器や浄化槽、換気扇、換気口などは定期的に点検し誤作動していないかチェックしましょう。
生活を維持できない設備の故障には必ず気づきますが、故障やトラブルに気づくことが少ない設備は注意が必要です。
例えば、換気扇は目詰まりや油の付着による害虫の発生があっても気づかないことがあります。換気口はコウモリの巣になることもあり、糞尿によって汚染された空気を家屋内に循環させることにも繋がるでしょう。
このようなトラブルは、壁紙や木部にダメージを与える要因のため、必ず定期的に点検することをおすすめします。
修繕や改修工事
ある程度築年数が経過した家であれば、壁紙や床、和室のリフォームなどをおすすめします。
また、外壁と屋根は10年ごとに塗装工事と防水処理を実施し、防蟻処理も忘れずに実施しましょう。メーカーの長期保証を受けている家であれば、必須ともいえるでしょう。
このように、正しいメンテナンスを正しいタイミングで実施することで、家を長寿命にできる可能性が上がります。
家の寿命が近づいた時の対処方法
ここからは、家の寿命が近づいた時の対処方法を解説します。
- ・全面リフォームする
- ・建て替えを検討する
- ・売却する
家は、定期的に正しいメンテナンスを実施していても必ず寿命が訪れます。したがって、代表的な上記の対処方法を押さえておきましょう。
全面リフォームする
家の全面リフォームは、家の寿命が近づいた際の対処方法として有効です。
100㎡の2階建て木造住宅を全面リフォームするためには、約500〜1,000万円の費用がかかるといわれており、リフォーム内容によって大きく変わります。
そのため、まずは現在修繕が必要な部分と将来を見越して修繕しておいた方がよい部分を優先的にリフォームし、最適な費用で家の寿命を少しでも伸ばすように対策しましょう。
建て替えを検討する
築年数が経過し過ぎている家は躯体の劣化が激しく、家の安全をリフォームでは保てないケースもあります。その場合は、建て替えがおすすめです。
居住地を変えることなく家だけを新しくすることで、移住によるストレスをなくすことにもなります。また、家の資産価値も大きく上昇することになるため、相続資産としても有効だといえるでしょう。
売却する
居住地を変えてよい場合は売却しましょう。寿命が近づいた家の対処方法としては、最も工数がかからない方法だといえます。
新しいエリアでの生活にストレスを感じることもありますが、安心して住める住環境を得られるメリットは非常に大きいでしょう。
家の寿命とリフォームの関係性
ここでは、リフォーム後に何年住めるのか、築年数ごとに解説していきます。
- ・築20年の家をリフォームすると何年住める?
- ・築30年の家をリフォームすると何年住める?
- ・築40年の家をリフォームすると何年住める?
- ・築50年の家をリフォームすると何年住める?
現在住んでいる家の築年数に応じて、今後どのくらい居住できるのかの目安にしてください。
築20年の家をリフォームすると何年住める?
築20年の家は、設備の不備も少なく給湯器交換といった軽微なリフォームだけで問題ないといえるでしょう。ただし、外観の状態によっては外壁と屋根を塗装する必要があります。
家の寿命としての期間はまだ残されているので、適切な処置を施すことで30年以上住み続けられる築年数だといえます。
築30年の家をリフォームすると何年住める?
築30年を経過したあたりから、家の床鳴りや壁紙の剥がれ、窓サッシ周辺部分の木部損傷が目立つようになります。ただし、寿命で見ると家の耐久性は保たれている環境です。
したがって、10年周期で実施する外壁塗装や屋根塗装、防水処理などは必ず実施し、気になる点を修繕するだけで20年以上は住める状態だといえます。
築40年の家をリフォームすると何年住める?
築40年を経過した家は、これまでの使い方によって大きく状態が変わります。
つまり、正しくメンテナンスされている家であれば、その先も10年以上住めるものの、そうでない家は倒壊の恐れがある状態です。
そのため、建て替えを含めた検討が必要な時期だといえるでしょう。
築50年の家をリフォームすると何年住める?
築50年を超えた家は、耐震検査などを実施するなど耐震補強が必要な時期となります。
ただし、耐震補強工事は1,000万円を超えるケースもあるため、リフォームやリノベーションよりも建て替えのほうが望ましいでしょう。
築50年を超えた家は、今後10年以上も住み続けられる可能性があるとしても、それ以下で考えておくべきタイミングといえます。
家の寿命に合った対処方法を施して、長く快適な生活を送ろう
家の寿命は住宅構造に関わらず、メンテナンスの頻度や家の使い方によって大きく変わることがわかりました。そのため、築浅物件の時期からしっかりと手入れすることで、住環境を長く維持できます。
国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。
・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない…
・マイホームに必要な資金って具体的にいくら?
・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要?
・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能?
といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。
国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から!
https://kh-house.jp/event/