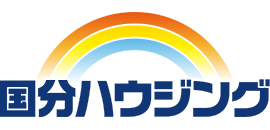Blog / Column
スタッフブログ・コラム
家づくりコラム
建物・家づくりについて
土地探しについて
2023.02.28
敷地面積とは?建築面積・延床面積との違いや制限をわかりやすく解説

注文住宅を検討する際には、敷地面積や建物面積、延床面積といった言葉をよく目にすることがあります。それぞれ建築する上で重要なポイントになるものの、建築会社から説明を受けても内容が難しく理解できていない人も少なくありません。
この記事を参考にしながら、それぞれの特徴を理解しましょう。
| 【この記事でわかること】
● 敷地面積と建築面積・延床面積の違い ● 建築面積に含まれない間取りの特徴 ● 延床面積に含まれない間取りの特徴 |
敷地面積とは
敷地面積とは、土地全体の面積のことです。
土地の物件資料に記載されている土地面積は敷地面積となっていますが、敷地面積には「公簿面積」と「仮測量面積」、「確定測量面積」があります。
そのため、次に挙げる特徴を把握した上で物件資料に記載されている面積がどれにあたるのかを確認することが重要です。
| 種類 | 特徴 |
| 公簿面積 | 法務局に備え付けられている、全部事項証明書に記載されている面積 |
| 仮測量面積 | 土地家屋調査士が土地を測量し、所有者の承諾を得る前の面積 |
| 確定測量面積 | 仮測量の結果に基づいて土地所有者と周辺所有者の押印を得た状態の面積 |
仮測量面積は所有者の承諾を得る前の面積となり、公簿面積よりは正確な面積です。確定測量面積は、登記することで新たに公募面積となるため、最も正確な面積といえます。
敷地面積と建築面積・延床面積の違い
この章では、建築面積、延床面積を解説しながら、敷地面積との違いを明確にしていきます。
それぞれ建築する上で重要な指標となるため、家づくりを始めるタイミングまでにしっかり理解しておきましょう。
- 建築面積とは
- 延床面積(建物面積)とは
順番に解説していきます。
建築面積とは
建築面積は「水平投影面積」とも呼ばれ、建物を上空から見た際の面積のことです。最も投影面積が広い階層の面積が適用されることになり、建物の面積を表すわけではありません。
建築面積は、土地に対する建築面積を制限する「建ぺい率」の計算に使用され、建ぺい率60%の地域であれば、50坪の土地に建築面積が30坪以下の家を建築できることになります。
このように、建築面積は建築する建物の面積に大きな影響を与える面積だといえるでしょう。
延床面積(建物面積)とは
延床面積は建物全体の総床面積となり、柱や壁の中心から内側にある全ての床面積を合計した面積となります。
建築面積が建ぺい率の計算に使用される一方で、延床面積は容積率の計算に使われます。
容積率は、土地面積に対しての延床面積倍率を制限した割合です。たとえば、容積率200%の地域で50坪の土地に建築する場合は、延床面積を100坪以内に設計する必要があります。
このように、前述した建築面積と合わせて建築を制限するために使用されるのが、延床面積となります。
住宅の面積に関するさまざまな制限
住宅は、建ぺい率と容積率による制限を受けることを解説しましたが、それ以外にも「高さ」に関する制限を受けることになります。
- 日影規制
- 斜線規制
- 接道義務
この章では、建築基準法で定められる上記3点の高さ制限について、霧島市役所が公開している『霧島市用途地域別制限一覧』のデータを参考に解説します。
日影規制
日影規制は、家が作る影に制限を設けた規制です。1年で最も日が長くなる冬至の8時〜16時(北海道の場合は8時〜15時)に生じる影が測量対象となります。
日影規制は用途地域によって規制内容が変わり、たとえば霧島市の第1種低層住居専用地域だと10m以内は4時間、10mを超える部分は2.5時間となります。
このように、家を建てることで隣地の日照に大きな影響を受けないように制限することが、日影規制の目的です。
斜線規制
斜線規制とは、道路もしくは隣地の境界に対し、ある一定の角度に建物が斜線しないよう制限した規制です。
この規制は、日光や風通りが確保できる街を維持することが目的で設けられています。
たとえば、霧島市の第1種低層住居専用地域では、道路の端面から1.25の勾配ラインを20m引き、その間に建物が来ないよう制限されることになります。
斜線規制には道路斜線や隣地斜線、北側斜線の3種類があり、どれも非常に複雑な勾配計算が必要です。したがって、無理に自分で計算せず建築会社に現地を確認してもらい、制限をクリアした建築が可能かどうかを見極めてもらいましょう。
接道義務
接道義務とは、敷地に建物を建てる場合に、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければならない決まりです。
鹿児島県には道路の接道に関して許可基準が設けられており、建築するためには4m以上の道路に2m以上設置しなければなりません。ただし、4m未満であっても規定の面積をセットバックすることで建築許可がおりるなど細かなルールがあります。
このように、道路が4m未満の土地を検討する場合は、必ず不動産会社か建築会社に現地確認してもらいましょう。
建築面積は建ぺい率によって制限される
前述したとおり、建築面積は建ぺい率によって大きく制限されます。
建ぺい率の制限は、圧迫感のある街並みとならないための措置や、延焼のリスクを下げる効果があるため、鹿児島県以外の都道府県でも設定されています。
そのため、家づくりを検討する場合には土地や建物だけでなく、規制されている法令についても調べることが重要です。
建築面積はバルコニーやひさしは含まれるのか
結論からいうと、バルコニーやひさしは建築面積に含まれません。
建築面積は上空から測定した面積となるものの、バルコニーやひさしは建築部位として算出しないのが原則です。
ただし、2mを超えるバルコニーや屋根があり部屋の内部に設置するインナーバルコニーなどは、建築面積に含まれる部分があるため注意が必要です。
延床面積に含まれない箇所
この章では、延床面積に含まれない箇所を解説します。
- 出窓
- ベランダ・バルコニー
- 吹き抜け
- ロフト
- 外部階段
延床面積が小さくなると容積率の条件をクリアしやすくなり、建物の固定税も低くできます。
この章で解説する各箇所のポイントを押さえ、最適な延床面積を目指しましょう。
出窓
出窓は、家の外に向かって出っ張ったような設計の窓を指し、窓の下部にスペースがあり小物などを飾れます。
出窓は、延床面積を減らしつつ家屋内のスペースを増やすためによく使われる間取りです。
奥行きが50cm未満、床からの高さが30cm以上、床から1.35mの高さに半分以上の窓があるなど、細かい規定があることを押さえておきましょう。
ベランダ・バルコニー
ベランダやバルコニーは、2m以内まで延床面積から除外できます。
ただし、2mを超えたベランダやバルコニーは全て延床面積となるわけではなく、超えた部分のみ除外となることを把握しましょう。
それ以外にも、格子を取り付けると延床面積に含まれるなど、市区町村が独自に設定しているルールもあるため、間取り採用時には注意が必要です。
吹き抜け
吹き抜けは床自体がないため、延床面積には含まれません。
開放的な空間の演出と採光を多く取り入れられるため、玄関などに導入するケースが多くあります。ただし、吹き抜けの2階は床がなく部屋として利用できないため、部屋の広さを十分に確保できる間取りを意識しましょう。
ロフト
ロフトは、デッドスペースを有効活用するために導入される間取りで、部屋を効率良く使用したい人に人気です。
ロフトはあくまでも「部屋」ではないため、延床面積に含めず設計できる一方で、さまざまな制限があります。
制限内容は市区町村によって異なる部分が多いため、必ず建築会社に問い合わせて、制限内容を確実に確認した上で検討しましょう。
外部階段
二世帯住宅などで設置される外部階段は、いかなる形状、角度であっても延床面積に含まれません。したがって、延べ床面積を計算する際には、まず外部階段を除外し計算しましょう。
敷地面積・建築面積・延床面積に関するよくある質問
最後に、敷地面積・建築面積・延床面積に関するよくある質問を紹介します。
- マイホームの一般的な広さはどのくらい?
- 駐車場を設ける場合に敷地面積はどれくらい必要?
- 敷地面積・建物面積・延床面積の平均はどれくらい?
マイホームの一般的な広さはどのくらい?
『住宅金融支援機構』のデータによると、全国と首都圏では123.8㎡、近畿圏は127.1㎡、東海圏は123.5㎡、そのほかの地域では123.1㎡が平均的な広さです。
なお、鹿児島県の平均は107.6㎡となっています。
駐車場を設ける場合に敷地面積はどれくらい必要?
『一般財団法人自動車検査登録情報協会』で定められる車両サイズにもとづき、スーパーマーケットや、ショッピングモールに設置されている駐車場は、2.5×5mのサイズであることがほとんどです。
ただし、並列に並べた場合は少々圧迫感があるため、「3m×6m=18㎡」を駐車場用地として検討することをおすすめします。
敷地面積・建物面積・延床面積の平均はどれくらい?
建物面積と延床面積は前述した通りとなり、敷地面積は中央値を平均とした場合に全国および首都圏、近畿圏で100㎡〜110㎡が平均となりました。
また、それ以外のエリアとして東海圏では160〜170㎡、そのほかの地域では230〜240㎡が平均値となっており、鹿児島県の平均においても同様の230〜240㎡となります。
敷地面積・建物面積・延床面積の特徴や違いを理解しよう
敷地面積と建物面積、延床面積は家づくりにおいてそれぞれが重要なポイントとなっており、理解したほうがよい面積といえるでしょう。
そのため、それぞれの面積は家づくりをスタートする前に、しっかりと押さえておくことをおすすめします。
国分ハウジングでは、鹿児島県に特化した建築プランを提案しております。土地を最大限に有効活用した家を建てたい人は、ぜひ国分ハウジングまでお問い合わせください。
| 来場予約|国分ハウジング |