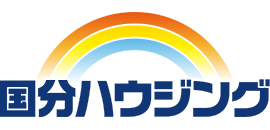Blog / Column
スタッフブログ・コラム
家づくりコラム
土地探しについて
2022.11.30
底地と借地は何が違う? 底地の買取・売却までわかりやすく解説

不動産売買を進める際に「底地」と「借地」という言葉をよく聞きます。特に、土地を賃借するという選択をした際には、2つに対する理解が重要になるでしょう。
そこで本記事では、底地と借地の違いや設定した場合のメリットやデメリット、注意点について解説します。
| 【この記事でわかること】
● 底地の特徴や借地との違い ● 底地のメリット・デメリット ● 底地を売買する際の注意点 |
そもそも底地とは?
底地とは、借地権が設定されている土地の呼び名です。
- 底地の定義
- 底地の種類
- 底地の売却方法
ここでは底地の特徴について解説します。
底地の定義
土地を貸す際には借地権が設定されることがあり、地主側から見たときの土地所有権を底地と呼びます。なお、「底地」というワードは地主側にのみ使用されることを覚えておきましょう。
底地の種類
底地には大きく分けて3つの種類があります。
- 普通借地
- 一般定期借地
- 事業用定期借地
それぞれ以下のような特徴があります。
<普通借地>
土地を貸す期間が最短で30年となっており、借地人が更新できる底地です。
地主は、正当な理由なしに更新を拒否できず、さらには地主の同意なく建物買取請求権が行使されてしまいます。また、正当な理由があったとしても、借地人が使用を継続しそれについて異議申し立てをしなかった場合は無効です。
このように、地主にとって非常に不利な契約形態となるため、底地の設置時には慎重に検討しましょう。
<一般定期借地>
借地人が更新できない借地の1つに、一般定期借地があります。
契約期間の最短期間が50年と長いものの、正当な理由なく時期の到達時点で契約満了による解約となります。このように、普通借地よりも地主に配慮した内容となっているのが特徴です。
2022年現在では「使用する用途がないけれど、必ず土地を返却してもらいたい」などの場合に幅広く利用される借地権といえます。
一般定期借地は、一般住宅やマンションを建築する際の底地として利用されることも多く、フレキシブルな土地活用を進められる借地権だといえるでしょう。
また、一般定期借地によく似た借地権として、30年経過後に地主が建物を買い取りすることで契約を満了にできる「建物譲渡特約付借地権」という形態もあります。
あまり利用されるケースはありませんが、一般定期借地と同様に、地主が正当な理由なく買取した時点で契約満了とできます。そのため、土地活用を方針転換する可能性がある場合には効果的な借地権だといえるでしょう。
<事業用定期借地>
一般定期借地が一般住宅やマンション用の借地権であるのに対し、事業用定期借地は事業に特化した定期借地権です。期間は10〜50年と幅広く、一般借地と同様に地主の正当な理由も買い取り請求もありません。
建物の使用用途が一般定期借地とは違いますが、そのほか、契約は公正証書にする必要があるという点が違います。公正証書にすることで、契約期間が短い場合の権利濫用を防止でき、借地人を守れます。
上記は、平成4年に施行された改正借地借家法に基づいた分類です。したがって、平成4年よりも前から設定されている旧借地法に該当する土地は対象外となるので注意しましょう。
このように、一般定期借地にするか、事業用定期借地にするかは土地の活用方法によって選択肢が分かれます。
どちらが正しい設定になるのかは、しっかりと不動産のプロに相談して選びましょう。
底地の売却方法
底地は性質上、地主が自由に使用できる土地ではありません。
そのため、売却するために販売開始したとしても一般住宅を建築できるわけではないため、買い手がつかない可能性は高いといえるでしょう。
そこで、底地の売却はあくまでも収益物件として売却することをおすすめします。
契約残存期間が短く固定資産税以上の賃料を得られる底地であれば、収益としての価値は十分に見込めるといえるでしょう。
このように、買い手のターゲット層を変えることで底地の売却が成功する可能性はあるといえます。
底地と借地の違い
底地は地主が保有する土地を貸し出し、借地権が設定された土地のことです。
一方、借地は底地の上に建っている建物を指します。「借地」という呼び名で建物を表すことに違和感がある人も少なくありませんが、便宜上の表記だと考えておきましょう。
固定資産税と都市計画税はどちらにかかる?
固定資産税と都市計画税は所有者が負担する税金です。そのため、土地については地主、建物については借地人がそれぞれ税負担することになります。
ただし、借地権が設定されている底地は通常よりも固定資産税評価額が安くなっています。そのため、借地権を解除すると固定資産税と都市計画税が増額されるので注意しましょう。
底地のメリット
地主が底地を保有するメリットには、どのようなポイントがあるのでしょうか。今後、借地権を設定する際には以下のメリットを検証し、有効だと判断できる場合に進めましょう。
- 賃貸収入を得られる
- 税金が抑えられる
- 管理しやすい
賃貸収入を得られる
全く活用していない土地であっても、固定資産税と都市計画税は毎年かかってしまいます。
そこで、底地にすることで賃貸収入で税金を補填する方法が有効です。
税金が抑えられる
固定資産税などの評価額は路線価をベースに算出されます。また、地域ごとに借地権割合が設定されており、その割合に基づいて評価額が計算されます。
例えば、鹿児島県鹿児島市にある江南中学校の西側道路には、路線価が175,000円/㎡、借地権割合は40%に設定されています。
つまり、50坪の土地であれば約2,900万円の評価額ですが、借地権割合を考慮すると評価額を約1,200万円まで抑えられます。それに伴って、大きな減税効果を得られるでしょう。
※参考:財産評価基準書|国税庁
管理しやすい
借地権は駐車場などと違い特定の人が利用するため、管理トラブルが少ないという特徴があります。
さらに、地上にある建物は借地人の管理責任となるため、地主は賃料収入を得るのみで何も管理することがないというケースもあるでしょう。
底地のデメリット
底地は節税効果も高く管理しやすいというメリットがある一方で、通常の土地とは異なるデメリットも多いといえます。
- 自由に使用できない
- 条件次第で税金がかかる
- 不動産売買に制限がかかる
ここでは、底地を保有するデメリットについて解説します。
自由に使用できない
どのような借地権の形態であっても、最短で10年間は自由に土地を利用できません。土地を突然売却することになったとしても、借地人の許可を得ることは困難といえるでしょう。
このように、底地には所有権を保有しながらも、長年にわたって利用が制限されるというデメリットがあります。
条件次第で税金がかかる
年間20万円以上の賃料収入が発生した場合、不動産所得として税金がかかります。また、経費として固定資産税や都市計画税を加算できないため、注意が必要です。
不動産売買に制限がかかる
底地を第三者へ売却する際には様々な制限があり、契約形態によって買い手の負担が非常に大きくなるケースもあります。
例えば、買い手が変わると公正証書の継承ができず、新たに地主と借地人の間で公正証書を作成するというケースもあります。また、底地を購入する際に抵当権が設定できず、銀行から融資を得られないという場合も多く見受けられます。
このように、通常の土地売買では起きないトラブルが発生するため、底地の売却は慎重に進めましょう。
底地を売買する際の注意点
底地を売買する際には、次の注意点を押さえましょう。
- 書類の有無と内容を確認しておく
- 底地を売却する際は借地人に声をかける
- 建物登記が借地人であるかを確認する
買い手からすると、購入した土地が思い描いていた土地ではなく、その結果多大な損失となることもあります。上記を怠ると最悪の場合、裁判となるケースも多いため、トラブルが発生しないように必ず事前準備することが重要です。
書類の有無と内容を確認しておく
底地の売買時には、書類の有無が非常に重要です。
なぜなら、売却をフォローする不動産会社は公正証書や借地契約書の内容を見て売却価格を決めるからです。そのため、書類に不備や紛失があった場合は売却できない可能性もあります。
また、契約の残存期間や建物買取請求権の有無も、買い手にとっては重要なポイントになるため、売買開始前にあらかじめ確認しましょう。
底地を売却する際は借地人に声をかける
底地を売却する際、買う可能性が高いといえる買い手は借地人です。
借地人にとっては、毎月の家賃を支払う必要がなくなり、さらには土地を所有することで建物の資産価値も大きく上昇することになります。
したがって、底地を売却する際にはまず借地人にその旨を伝え、購入の意思がないのかを確認しましょう。
建物登記が借地人であるかを確認する
借地契約を締結した借地人と建物所有者が違う場合、借地権が認められないという判例があります。
これは、土地を貸す際の信義則に反しているという法解釈によるもので、たとえ建物名義人と借地人が親子関係であっても、地主と建物名義人に信頼関係があるとはいえないからです。
底地を購入した買い手は家賃収入を得る権利がないとされ、重大なトラブルに発展する可能性があるため、建物名義人は必ず確認しましょう。
底地に関するよくある質問
ここでは底地に関するよくある質問に回答します。
- 借地権者が底地を買い取ることはできる?
- 底地と更地の違いは?
- 底地ビジネスってなに?
借地権者が底地を買い取ることはできる?
借地権者が底地を買い取るケースは非常に多く、底地を売却する際にはまず借地権者に声をかけるのがセオリーです。
ただし、銀行によっては底地購入には融資しないと判断されるケースがあるため、あらかじめ銀行に確認する必要があります。
底地と更地の違いは?
底地は借地権が設定された土地であり、更地は建造物がなく、借地権などの権利の設定されていない土地を指します。
底地ビジネスってなに?
底地ビジネスとは、底地を収益物件として購入して家賃収入を利益とするビジネスです。
安い代金で土地を購入し、ランニングコストを家賃収入で賄い、将来自由に土地活用できます。そのため、大手企業だけでなく一般の投資家にも注目の投資だといえます。
良い点が多い底地ビジネスですが、天災などの影響で土地の価値が大幅に下落したり流動性が極めて悪かったりなどのデメリットもあるため、底地ビジネスを始める前には入念なリサーチが必須となるでしょう。
底地の特徴を正しく理解して売買取引を成功させよう
底地は一度設定すると10年以上土地の活用方法が制限されるため、慎重に検討する必要があります。その一方で、税金を大きく下げられるメリットもあり、正しい手順を踏めば売却することも可能です。
国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。
・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない…
・マイホームに必要な資金って具体的にいくら?
・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要?
・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能?
といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。
国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から!
https://kh-house.jp/event/