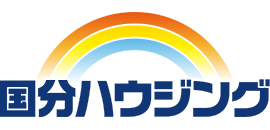Blog / Column
スタッフブログ・コラム
家づくりコラム
資金(ローン)について
2022.11.08
住宅ローン控除を利用する条件は?計算方法や手続き・注意点も詳しく解説

住宅ローンは土地購入に利用できる?ローンの種類やメリット・流れを解説
住宅ローン控除を利用する条件は?計算方法や手続き・注意点も詳しく解説
住宅ローンを利用する場合、条件を満たすことで住宅ローン控除を受けることが可能ですが、条件について詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。
住宅ローン控除を利用することで、支払う税金の負担を抑えてお得に家を手に入れることが可能です。
そこで今回は、住宅ローン控除の利用条件について、計算方法や注意点なども押さえながら詳しく解説していきます。
そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、家の購入で住宅ローンを利用した人を対象に、支払う税金の負担を軽くすることを目的とした制度です。
控除額は所得税から差し引かれ、所得税だけでは控除しきれない場合は住民税からも控除されることになっています。
住宅ローン控除を利用する物件の条件
住宅ローン控除を利用する条件は、対象となる物件によって異なります。
- 全ての住宅に共通する条件
- 新築物件の条件
- 中古物件の条件
- 増築・リフォーム物件の条件
上記4つの項目に分けて、詳しく解説していきます。
全ての住宅に共通する条件
全ての住宅において必要な条件の1つは、住宅ローンの契約者本人が居住するということです。
例えば、購入した本人が住まずに他人が居住するといった場合は、住宅ローン控除を受けられません。
また、返済期間が10年以上であるという条件もあります。
住宅ローンは、10年以上の返済期間であるケースがほとんどですが、稀に短い期間での契約となっている場合もあるので、注意しましょう。
ほかにも、所得額の合計が2,000万円以下であることも必要です。
以前は3,000万円以下という条件でしたが、2022年の改正により2,000万円へ条件が引き下げられたので、覚えておきましょう。
さらに、対象となる住宅の床面積についても条件があり、合計50㎡以上であることが必要とされています。
新築物件の条件
新築物件を購入した場合は、床面積に関する条件が個別で設けられています。
通常、床面積の合計は50㎡以上であることが条件とされていますが、新築物件の場合、所得額によって40㎡以上という条件が採用されるケースがあるので、覚えておきましょう。
所得額が1,000万円以下である人が新築物件を購入し、2023年までに建築確認を受けた場合に限り、床面積の条件が40㎡以上となります。
条件に該当する場合は、頭に入れておきましょう。
中古物件の条件
中古物件を購入する場合は、建物の安全性を考慮した条件が設けられています。
古い物件の場合、耐震性に問題がある可能性が考えられることから、1982年以降に建築されていることが条件とされているため、購入する物件の築年数を確認することが大切です。
また、1982年以前に建築されている場合でも、現行の耐震基準を満たしていると認められる物件であれば、住宅ローン控除を受けることが可能となっています。
増築・リフォーム物件の条件
増築やリフォーム物件についても、条件が複数設けられています。
まず把握しておくべき点は、費用に関する条件です。
増築やリフォームにかかる費用が100万円を超えていることが条件とされています。
そして、かかった工事費の半額以上が、居住用の箇所に使われていることも必要です。
ほかにも、修繕する箇所が大規模に渡ると判断されることが必要な条件として定められているので、住宅ローンを利用して増築やリフォームをする際は、控除の対象となるかどうかをよく確認しましょう。
住宅ローン控除の対象となるローン
住宅ローン控除の対象となるローンについても、把握しておきましょう。
控除を受けるには、借入先が住宅ローン控除の対象となっていることが必要です。
例えば、銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関や、住宅金融支援機構、地方自治体などが対象となります。
自分が住む住宅を購入するための借入れであっても、知人から借入れる場合や、自身や親族が経営する企業から借入れる場合は対象外となるので、注意しましょう。
【2022年最新版】住宅ローン控除の計算方法
住宅ローン控除の計算方法は、以下の表を参考に把握しておきましょう。
| 居住開始時期 | ローン限度額 | 控除率 | 控除期間 | 年間最大控除額 | |
| (新築)
長期優良住宅 低炭素住宅 |
2022~2023年
2024~2025年 |
5,000万円
4,500万円 |
0.7% | 13年 | 35万円
31.5万円 |
| (新築)
ZEH住宅 |
2022~2023年
2024~2025年 |
4,500万円
3,500万円 |
0.7%
|
13年 | 31.5万円
24.5万円 |
| (新築)
省エネ基準適合住宅 |
2022~2023年
2024~2025年 |
4,000万円
3,000万円 |
0.7% | 13年 | 28万円
21万円 |
| (新築)
その他の住宅 |
2022~2023年 | 3,000万円
|
0.7% | 13年 | 21万円 |
| (中古)
定長期優良住宅 低炭素住宅 ZEH住宅 省エネ基準適合住宅 |
2022~2025年 | 3,000万円 | 0.7% | 10年 | 21万円 |
| (中古)
その他の住宅 |
2022~2025年 | 2,000万円 | 0.7% | 10年 | 14万円 |
| リフォーム・増改築 | 2022~2025年 | 2,000万円 | 0.7% | 10年 | 14万円 |
新築住宅の場合は特に、居住開始時期を注意して確認しましょう。
居住開始時期によって、ローン限度額や控除額の上限が異なります。
また、住宅の性能によって詳細が変わってくるという点も理解しておきましょう。
住宅ローン控除額は、年末におけるローン残高×控除率0.7%を計算した上で、年間最大控除額と比較し、金額が低いほうが実際の控除額となります。
住宅ローン控除の手続き方法
住宅ローン控除を受けるために、手続き方法についても把握しておきましょう。
- 申請の流れ
- 必要書類
- 申請する時期
上記3つの項目に分けて、解説していきます。
申請の流れ
まずは、住宅ローン控除の申請の流れを解説します。
控除を受けるためには、住宅を購入してから半年以内に居住を開始しましょう。
住み始めたら、申請に必要な書類を準備し、確定申告の際に控除を申請するという流れになります。
必要書類
住宅ローン控除の申請手続きに必要な書類は、年末におけるローンの残高証明書、登記事項証明書、住宅を取得した際の契約書、源泉徴収票、住民票(写し)です。
スムーズに申請するために、余裕を持って各書類を準備しておきましょう。
申請する時期
住宅ローン控除の申請は、住宅を購入した翌年の確定申告の時期に行います。
住宅を購入した時期によっては、申請時期までに長い期間が空くケースも多くありますので、忘れないように把握しておきましょう。
住宅ローン控除を利用する際の注意点
住宅ローン控除を利用する際は、以下の4点に注意しましょう。
- 確定申告する必要がある
- 1年目と2年目以降で手続き方法が異なる
- 手続きを忘れた場合は還付申告が必要になる
- 住宅ローンの繰り上げ返済や借り換えタイミングに注意する
確定申告する必要がある
住宅ローン控除を申請するためには、購入した翌年に確定申告する必要があります。
会社員の場合、通常であれば毎年年末調整のみで済むケースが多いので、住宅ローン控除を受ける年は自分で確定申告しなければならないことを覚えておきましょう。
1年目と2年目以降で手続き方法が異なる
住宅ローン控除は、住宅を購入してから10年以上に渡って受けられますが、1年目と2年目以降で手続きの方法が異なる点に注意が必要です。
1年目の手続きに関しては、前述の通り確定申告にて申請しますが、2年目以降は勤め先の年末調整で申請することになります。
手続きを忘れた場合は還付申告が必要になる
万が一住宅ローン控除の申請手続きを忘れてしまった場合は、還付申告が必要になります。
還付申告には期限があるので、手続きを忘れたことに気付いた際は早めに申告しましょう。
住宅ローンの繰り上げ返済や借り換えタイミングに注意する
住宅ローンの繰り上げ返済や借り換えをする場合は、タイミングに注意しましょう。
繰り上げ返済や借り換えによってローン残高が少なくなると、受けられる控除額も減ってしまいます。
タイミングによっては繰り上げ返済や借り換えをしないほうがお得になるケースもあるので、損をしないようなタイミングをよく確かめるようにしましょう。
住宅ローン控除に関するよくある質問
ここでは、住宅ローン控除に関するよくある質問を2つ紹介します。
- 住宅ローン控除の確定申告を本人以外が代理で行うことはできる?
- 2022年の住宅ローン控除の大きな変更点は?
それぞれ回答とあわせて見ていきましょう。
住宅ローン控除の確定申告を本人以外が代理で行うことはできる?
住宅ローン控除の確定申告は、原則として本人以外が代理で行うことはできません。
たとえ家族内であっても代理申請は禁止されているので、注意しましょう。
ただし、病気などにより申請が困難な場合は、書類の記入と提出に限り、代わりに行うことが認められています。
2022年の住宅ローン控除の大きな変更点は?
2022年の住宅ローン控除の大きな変更点は、控除率と控除期間です。
控除率は1%から0.7%へ変更され、控除期間は一律10年間であったのが、新築住宅に限り最長13年間となりました。
また、控除を受けられる所得額の上限が、3,000万円から2,000万円に下がったのも、大きな変更点の1つです。
住宅ローン控除を利用してお得に住宅を取得しよう
マイホームを購入する際は、住宅ローン控除の利用について理解を深めておきましょう。
住宅ローン控除を利用することで、支払う税金の負担が軽くなり、お得に住宅を取得できます。
国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。
・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない…
・マイホームに必要な資金って具体的にいくら?
・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要?
・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能?
といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。
国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から!