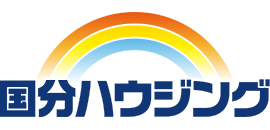Blog / Column
コラム
-

擁壁とは?種類や費用・注意点をわかりやすく解説
希望のエリアで土地を見つけたとしても、必ずしも平らな土地であるとは限りません。 敷地内や敷地に隣接する部分に高低差がある場合、「擁壁」を組む必要があります。しかし、擁壁の造成費は高額になることが多く、資金計画が成立しないケースは少なくありません。 そこで本記事では、擁壁の種類や費用、注意点について解説します。擁壁を設ける必要がある人は、ぜひ最後までお付き合いください。 【この記事でわかること】 ● 擁壁の種類 ● 擁壁のある家を建てる際の注意点 ● 擁壁がある土地を購入する際のポイント 擁壁とは? 擁壁は「がけ」に隣接する土地で建築する際に、土圧や水圧によって地盤が崩壊し家が倒壊しないようにするための構造物です。 鹿児島県では地表面が水平面に対して30度を超え、さらに高さが2m以上ある高低差を「がけ」と定義しています。 このような「がけ」に隣接する場合、鹿児島県では建築基準法施行条例に戻づいた擁壁を建築し許可を得ることで、家の建築が可能となります。 ※参考:がけに近接する建築物について|鹿児島県 擁壁の種類 擁壁を造成する箇所はさまざまな地形になっており、擁壁も地形や用途に応じて種類が分けられます。そこで、この章では擁壁の種類を解説します。 RC造 大谷石積み擁壁 間知ブロック積み擁壁 順番に見ていきましょう。 RC造 RC造はコンクリート製の擁壁であり、鉄筋の有無によってSRC造とRC造に分けられます。 垂直に近い擁壁を組むことに特化しているため、家のすぐ横に擁壁を組む必要がある場合に使用されます。 大谷石積み擁壁 大谷石積み擁壁は「大谷石」と呼ばれる軽石凝灰岩の1種を積み上げた擁壁です。加工がしやすいことから、昭和時代に建築された建造物にはよく使われていました。 現在では、耐久性の問題から使用されることがほとんどない擁壁といえます。 間知ブロック積み擁壁 間知ブロック積み擁壁とは、城の石垣にも使われている擁壁のことで、斜面を造成する際に利用するケースが多くあります。 RC造よりも耐久性が劣るケースもあることから、間知ブロックでは建築要件を満たさないとするハウスメーカーもあります。 そのため、間知ブロックで造成されている土地は、ハウスメーカーにしっかり確認してもらう必要があるでしょう。 擁壁工事にかかる費用 土地に10m接面する部分に5mの擁壁を組んだ場合、一般的に600〜900万円の造成費が必要となります。そのため、安い土地でも結果的に予算を大きく超えるケースがほとんどです。 ただし、緊急性の高い擁壁工事については助成金や補助金が発生する可能性があります。 後述する条件に該当する場合は、積極的に利用することをおすすめします。 擁壁工事の助成金・補助金 鹿児島県には「がけ地応急防災工事費補助事業」という補助金制度があります。 この制度によって、30度以上かつ高さ5m以上のがけに隣接する土地に住んでいる場合、崩落を防ぐために必要な経費の50%(上限30万円)を補助金として受け取れます。 全ての擁壁工事が補助金対象となるわけではないため、該当する工事かどうかは不動産会社もしくはハウスメーカー経由で鹿児島県市役所に確認しましょう。 ※参考:鹿児島市がけ地応急防災工事費補助事業|鹿児島市 擁壁のある住宅にする場合の注意点 擁壁を組む際には、いくつかの注意点があります。 隣接する住宅とのトラブルに注意する 老朽化のリスクも考慮する 擁壁のある家に住んで後悔しないためにも、上記の注意点を事前に押さえましょう。 隣接する住宅とのトラブルに注意する 擁壁は、住宅と隣接していることが多く、トラブルにつながるケースもゼロではありません。 擁壁には維持管理責任があり、擁壁の所有者は適切に維持管理し保全する義務があります。 そのため、もし擁壁が破損し土圧や水圧によって隣地に土砂が流れた場合には、擁壁の所有者として原状回復させる必要があるでしょう。 また、擁壁を組むことで隣地の土地に影響がでる可能性もあります。このようなことにならないためにも、擁壁による影響と管理の有無についてハウスメーカーに相談しましょう。 老朽化のリスクも考慮する 家と同じように擁壁も劣化し、耐久性が低下します。 また、建築許可を取得し造成した擁壁であっても、将来家や土地を売却する際には擁壁を解体し、再度造成する必要があります。 このことからも、擁壁は老朽化によって資産として残りにくいことを把握しましょう。 擁壁のある住宅を購入する際のポイント この章では、擁壁のある住宅を購入する際のポイントを解説します。 現行の建築基準法を満たしているかを確認する 擁壁の適合があるかを確認する 高低差のある土地は、必ず購入者が擁壁を組むのではなく、既に擁壁があるケースもゼロではありません。 このような土地は、擁壁の造成費が不要になることもありますが、思わぬトラブルに巻き込まれることもあるため注意が必要です。 現行の建築基準法を満たしているかを確認する 現行の建築基準法を満たしているかどうかも、擁壁のある住宅を購入する上での注意点です。 大規模な分譲地であれば開発図面があり、擁壁の耐久力を調査した資料が残っている可能性もあります。資料があれば、現行法令に適合した擁壁のため、家を建築しても問題ないでしょう。 一方、個人が数十年前に組んだ土地の場合は現行の建築基準法に適合していない可能性が高く、その場合は解体し再造成する必要があります。 このようなことにならないためにも、開発許可の有無を確認することは重要です。 擁壁の適合があるかを確認する 新しい擁壁を組んでいたとしても、適合していないケースがあります。 たとえば、高低差が2m以内のがけに対して組んだ擁壁は任意設計の扱いとなるため、そのことに気づかなければ後々「違反」と通報されるおそれもあります。 また、任意設計の擁壁は不完全な整備によって、土圧の変化などで崩落する危険もあるので注意が必要です。擁壁がある土地は、リスクを回避するためにもしっかり調査しましょう。 擁壁で起こり得るトラブルと対策 擁壁に関するトラブルで最も多いのが、擁壁の「足」にあたる部分です。 擁壁は土圧で倒れないよう地中に足があり、L字の形状となっています。そして、足にあたる部分には建築できません。そのため、建築許可がおりている擁壁を組んだ場合、検討しているプランが通らないケースもあります。 また、擁壁を組むことで日当たりが悪くなるケースも少なからずあります。 どちらのトラブルにおいても、事前にハウスメーカーなどへ相談し、シミュレーションしておくことで防げるでしょう。 擁壁に関するよくある質問 最後に、擁壁に関するよくある質問を紹介します。 擁壁のある家にメリットはある? 擁壁の耐用年数は? 擁壁とコンクリートブロックの違いは? 擁壁のある家にメリットはある? 擁壁のある家は、日当たりがよく明るい家になる点がメリットといえます。 なぜなら、高低差があるため他の家よりも高台になるからです。 擁壁の耐用年数は? 正式な擁壁の法令耐用年数はありませんが、RC造で35年〜50年といわれています。 ただし、使い方や周辺環境によってはさらに長く保持できる可能性はあります。 擁壁とコンクリートブロックの違いは? 擁壁は、高低差のある土地で土圧や水圧で土地形状が変わらないようにするための建造物で、コンクリートブロックは土が流れないようにするための土留めです。 このように、擁壁とコンクリートブロックは用途が異なることを理解しておきましょう。 擁壁でトラブルを避けるためには地盤調査も視野に入れよう 擁壁があることで地盤が本来あるべき状態から変化し、家に思わぬ影響を及ぼすことがあります。対策として、擁壁のある土地は地盤調査することがおすすめです。 国分ハウジングでは、擁壁のある土地で安全に家を建てるためのノウハウがあり、建築実績も豊富です。土地探しでお悩みの方は、ぜひ国分ハウジングまでご相談ください。
-

一戸建てはメンテナンスが必要?必要箇所や修繕費用も解説
一戸建てを購入した場合、マンションと異なり自分でメンテナンスする必要があります。 一戸建ては、経年劣化によって耐久力が落ちる箇所や破損箇所を修繕することで長く住むことが可能となるため、どの部分を修繕すれば良いか把握しなければなりません。 この記事では、一戸建ての修繕が必要な箇所や費用について解説するので、これから一戸建てを検討する人は、ぜひ参考にしてください。 【この記事でわかること】 ● 一戸建ての寿命や耐用年数 ● 一戸建てをメンテナンスしなければならない理由 ● 一戸建てのメンテナンスが必要個所と時期 ● 一戸建てを長持ちさせるためのポイント そもそも一戸建ての寿命や耐用年数は? まずは、一戸建ての寿命や耐用年数を解説します。 戸建ての寿命 戸建ての耐用年数 順番に見ていきましょう。 戸建ての寿命 結論からいうと、戸建てに寿命はありません。 木造よりも鉄骨造の方が長く持つ傾向にありますが、木造も鉄骨造も決まった築年数で必ず倒壊するわけではありません。 そのため、定期的に戸建てをメンテナンスし丁寧に手入れすることで、きれいで安全な戸建てを維持できます。 戸建ての耐用年数 戸建ての耐用年数は構造によって変わるので、以下の表を参考にしてください。 構造 耐用年数 木造 22年 骨格材の肉厚3mm以下(軽量鉄骨) 19年 骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下 27年 骨格材の肉厚が4mmを超える 34年 ※参考:主な減価償却資産の耐用年数表 耐用年数とは、建造物を償却資産として経費計上できる年数のことで、家自体の耐久性とは厳密には無関係です。 ただし、会計上価値がなくなるタイミングは家の修繕箇所も増えるため、頭に入れておくことは重要です。 一戸建てのメンテナンスが必要な理由 一戸建てのメンテナンスが必要な理由は、主に以下の通りです。 住宅性能を長く維持して劣化を防ぐため 築年数が経過した場合でも劣化を防ぎ、資産価値をなるべく維持するため このように、快適な住環境を維持するためにも一戸建てのメンテナンスは必要といえます。 一戸建てのメンテナンスが必要な箇所と時期 一戸建ての設備や部位によってメンテナンスの時期が変わり、費用もさまざまです。そこで、この章では各部位のメンテナンス時期とおおまかな費用について解説します。 外壁、屋根 水回り 床(畳・クローリング) 内装(クロス) 順番に解説していきます。 外壁・屋根 外壁や屋根は、10年に1度のメンテナンスがおすすめです。なぜなら、多くの外壁塗装、屋根塗装の保証が10年であるからです。 紫外線を直接浴びる外壁と屋根は劣化がしやすく、劣化したまま放置していると剥がれやヒビが発生し雨漏りの原因になります。そのため、10年に1度は外壁と屋根を塗装しましょう。 なお、費用は30坪の家で120〜150万円が相場です。 水回り 水回りにはトイレやキッチン、台所、洗面台があり保証期間は5〜10年です。 そのため、保証が切れるタイミングでメンテナンスを検討するのも大事ですが、外壁や屋根と違い劣化が進みにくい部位といえます。 そのため、日頃の掃除を丁寧にすることで保証期間よりも長く使用でき、壊れた段階で交換しても問題ありません。 水回りの費用はトイレで5万前後、洗面台で10万前後、キッチンとトイレは70〜100万円が相場となります。 床(畳・フローリング) 床は10年を経過すると軋むようになり、畳は日焼けしたり虫食いが発生したりします。 このような現象が発生した場合はメンテナンスすべきですが、フローリングの張替えはリビングだけでも20万円程度が相場となり、家全体の張替えだと50万円以上の費用が必要でしょう。 そのため、フローリングの軋みはスポット的に調整し修繕することをおすすめします。 一方、畳は表替えで1万〜3万、全て新調で5万前後が相場です。畳は日焼けすると見た目が悪くなり、防虫効果が薄れることでダニが発生する可能性が高くなります。 ダニの発生はアレルギー物質を飛散させるため、早めにメンテナンスしましょう。 内装(クロス) 内装が浮いたり剥がれたりした場合、接着剤の効果が切れている可能性があります。 壁紙が剥がれ石膏ボードがむき出しになると、家の強度が下がり他の部位が破損することにもなりかねません。 そのため、壁紙の剥がれを発見した場合はすぐに張替えることをおすすめします。なお、内装の張替えはリビングだけで15〜20万円、家全体で70万円前後が相場となります。 【築年数別】一戸建てのメンテナンスで注意すべき箇所 この章では、築年数別に一戸建てのメンテナンスで注意すべきポイントを解説します。 築5~10年のメンテナンス箇所 築10~15年のメンテナンス箇所 築15~20年のメンテナンス箇所 築20~30年のメンテナンス箇所 築年数によってメンテナンス箇所の優先順位が変わるため、参考にしてください。 築5~10年のメンテナンス箇所 築年数が10年以内であればメンテナンスする箇所は少なく、突発の故障箇所のみで問題ありません。 ただし、このタイミングで外壁や床などに極端な異常が確認された場合は施工不良の可能性も考えられるため、施工会社に連絡することをおすすめします。 築10~15年のメンテナンス箇所 外壁や屋根塗装、防蟻処理は築10〜15年で実施しましょう。 また、給湯器は早ければ同時期に異常をきたすため、交換を検討することをおすすめします。 築15~20年のメンテナンス箇所 築15〜20年近くになると、床の軋みや壁紙の剥がれが出てくる可能性があります。 また、子どもの独立や同居など、家族構成が変化する時期でもあるため、床と壁紙に留まらず家全体のリフォームを検討する時期です。 築20~30年のメンテナンス箇所 築20年を超えると、これまでのメンテナンスによる影響が表面化してきます。 つまり、しっかりメンテナンスしている場合は前述した通りのメンテナンスで十分ですが、メンテナンスしていなければ、フルリフォームが必要な状態になるでしょう。 また、住み替えを検討する時期でもあるため、売却を踏まえてリフォームを検討するタイミングだといえます。 一戸建てのメンテナンスにかかる修繕費用 一戸建てのメンテナンスにかかる修繕費用は、以下の通りです。 メンテナンス箇所 修繕費用 外壁・屋根塗装 ・約120~150万円 トイレ ・約5万円 洗面台 ・約10万円 キッチン ・約70~100万円 バスルーム ・約70~100万円 給湯器交換 ・約10万円 フローリング張り替え ・約20~50万円 畳張替え ・表替え:約1~3万円 ・新調:約5万円 クロス張替え ・約20~70万円 一戸建てのメンテナンスは、外壁や屋根塗装のように定期的に実施する箇所もあれば、クロスや畳、床など破損した時点で実施する箇所もあります。 また、給湯器は破損してから交換すると日常生活に支障をきたすため、破損していなくとも交換タイミングを決めておくことがおすすめです。 家全体をフルリフォームする場合、約400〜500万円前後の費用になるでしょう。 一戸建ての寿命を長持ちさせるためのポイント この章では、長く快適な戸建てに住み続けるためのポイントについて解説します。 信頼できる施工会社に依頼する 外壁の状態をこまめにチェックする シロアリ対策を実施する 自分で掃除や換気をこまめに実施する 一戸建ての寿命を延ばすことで、メンテナンスの頻度と費用を抑えられます。 信頼できる施工会社に依頼する 一戸建てのメンテナンスは、リフォーム会社に依頼することをおすすめします。 外壁塗装や畳の張替などは建築業の免許が不要なため、専門業者でなくとも施工が可能です。 しかし、満足のいく仕上がりになるかどうかは職人による部分が多く、信頼できない施工会社に依頼すると中途半端な仕上がりで完成とされてしまうこともあります。 このように失敗しないためにも、信頼できる施行会社に依頼することが重要です。 外壁の状態をこまめにチェックする 外壁は普段目にすることがない分、経年劣化に気づかないケースも少なくありません。 特に、道路と反対側の外壁は日当たりが悪いことも多く、カビの発生などが懸念される箇所です。 外壁の劣化が進むと雨漏りの原因となり、雨水が一度でも侵入すると家のダメージが見えない箇所に蓄積してしまいます。その結果、メンテナンス間隔が早くなってしまうため、外壁は意識してチェックしましょう。 シロアリ対策を実施する 雨漏りと同じく、シロアリの被害に遭うと重要な木部が腐食し、壁紙の剥がれや異音の原因になります。 そのまま放置すると家が倒壊する危険もあるため、10年に1度は防蟻処理によるシロアリ対策を実施することが大切です。 自分で掃除や換気をこまめに実施する 日常的に、掃除や換気を自分で実施することも重要です。 床や壁のホコリや、汚れを取ることでダニやカビの発生を防止でき、換気をこまめに実施することで、家屋内の空気循環を促進し湿度を最適に保てます。 このような手入れを日常的に行うことで、家全体のメンテナンスコストを抑えられます。 一戸建てのメンテナンスに関するよくある質問 最後に、一戸建てのメンテナンスに関するよくある質問を紹介します。 一戸建てをメンテナンスしないとどうなる? メンテナンスしやすい家の特徴は? 家を直すお金がない場合はどうすればいい? 一戸建てをメンテナンスしないとどうなる? 一戸建てをメンテナンスせず放置した場合、外壁や屋根の塗装が剥がれ、雨漏りなどが発生するおそれがあります。 また、内装の剥がれによって耐久性が落ち、シロアリ被害に遭うと家の耐久性が下がり、倒壊のリスクを抱えることになります。 このようなことにならないためにも、一戸建ての定期的なメンテナンスは重要です。 メンテナンスしやすい家の特徴は? 一般的に、外観・内観共に正方形で凹凸のない家がメンテナンスしやすい家になります。 メンテナンスしやすい家を建てることも重要ですが、どのような家でも定期的なメンテナンスを怠らないように心がけましょう。 家を直すお金がない場合はどうすればいい? 事前にメンテナンス費用が支払えるような資金計画を立てることが重要ですが、どうしてもお金がない場合は、助成金や補助金を活用することも手段の1つです。 鹿児島県では、リフォームの内容によって助成金や補助金が交付されます。詳しくは、施工会社に相談し、利用できる補助金制度を確認しましょう。 ※参考:住宅に関する国の補助・減税・融資|鹿児島市 一戸建てのメンテナンスはタイミングが重要 一戸建ては、メンテナンスの頻度が少ないと家にダメージが蓄積されてしまい、極端に多いとトータルコストが高くなります。 そのため、適切なタイミングでメンテナンスする必要があります。本記事で解説した、築年数ごとのメンテナンス箇所などを事前に把握しながら、適切に対処していきましょう。 国分ハウジングでは、家づくりのプランだけではなく、メンテナンスに関するご相談も承ります。 お客様に寄り添いながら最適なプランを提案するので、ぜひお問い合わせください。
-

ハウスメーカーと工務店の違いとは?メリット・デメリットも解説
この記事では、ハウスメーカーと工務店の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。 注文住宅を検討する上で、ハウスメーカーと工務店のどちらに依頼するのかを悩む人は少なくありません。SNSやインターネットではどちらも魅力的な家が公開されており、ほとんど違いがないように思えます。 しかし、実際にはハウスメーカーと工務店には大きな違いがあるため、家づくりを始める前にしっかりと押さえておく必要があるでしょう。 注文住宅を検討している人は、本記事を参考にそれぞれの違いを把握しましょう。 【この記事でわかること】 ● ハウスメーカーと工務店の違い ● ハウスメーカーと工務店のメリット・デメリット ● ハウスメーカーに向いている人、工務店に向いている人 ハウスメーカーと工務店の基礎知識 そもそも、ハウスメーカーと工務店の定義は公的に定められているものではなく、それぞれの建築会社が「ハウスメーカー」か「工務店」のどちらかに分類しています。 ハウスメーカーとは? 工務店とは? まずは、それぞれの一般的な概要を解説していきます。ただし、ここで解説する内容はあくまで一般的な内容のため、参考程度に押さえておきましょう。 ハウスメーカーとは? ハウスメーカーは一部の地域を除き、全国に担当エリアがある建築会社のことです。 ハウスメーカーは、CMなどで大々的に広告していることが多く、注文住宅を検討している人が聞いたことがある建築会社の多くは、ほとんどハウスメーカーに分類されています。 工務店とは? 工務店はハウスメーカーと異なり、特定の地域で活動している建築会社が多くあります。 ハウスメーカーのように大々的な広告は少ないケースが多いものの、地域密着型の活動によって認知度は高くなるでしょう。 ハウスメーカーと工務店の違い ハウスメーカーと工務店は事業スタイルの違いによって、多くの違いがあります。 そのため、ハウスメーカーと工務店のどちらに依頼するのかを悩む場合は、まずは2つの違いを正確に知ることが重要です。 そこで、この章ではハウスメーカーと工務店の違いを詳しく解説します。 コストの違い 規模や施工エリアの違い 住宅プランの違い 施工の技術力や工期の違い アフターサービスやメンテナンスの違い どちらにも例外はありますが、どちらが自身に合っている建築会社であるのかを判断するための参考にしてください。 コストの違い 建物の本体価格は、ハウスメーカーよりも工務店の方が安くなり、建物面積(坪数)と価格の割合ではハウスメーカーが坪70〜100万円、工務店は坪50〜80万円といわれています。 ハウスメーカーの方が高くなる理由として、使用している建材やスペックの違い、広告料の上乗せ分などがあります。 そのため、予算を固定して建築会社を選定するのであれば、ハウスメーカー同士や工務店同士での比較がよいでしょう。 規模や施工エリアの違い 前述したように、ハウスメーカーは全国に支店を構えていることが多く、CMも全国ネットで広告しています。そのため、ほとんど全ての地域で施工依頼ができるでしょう。 一方、工務店は地方TVなどで局地的に広告しており、都道府県をまたいで対応することは少ないといえます。ただし、施工するエリアを狭めることで資本を集中させ、ハウスメーカーと遜色ないサービスを展開しています。 住宅プランの違い 注文住宅は、建材を全て自分で選ぶフルオーダー住宅と、ある程度決められたパッケージから選ぶセミオーダー住宅があり、ほとんどの建築会社はセミオーダー住宅を供給しています。 そして、紹介するパッケージはハウスメーカーの方が多く、イメージに近い家を簡単に選ぶことが可能です。一方で、工務店にもセミオーダーパッケージはあるものの、ハウスメーカーほどラインナップは多くない傾向にあります。 したがって、建物プランが明確に決まっていないのであれば、ハウスメーカーの方が理想の家を見つけやすいといえるでしょう。 施工の技術力や工期の違い ハウスメーカーと工務店において、施工技術自体に大きな差はありませんが、現場の管理方法が違ってきます。 工務店の場合は、自社の社員もしくは協力会社が施工しますが、管理できる棟数のみ請け負うことで、品質を安定させることが可能です。 一方、ハウスメーカーは工務店よりも着工棟数が多く現場管理は難しいですが、協力会社や社員研修をしっかり行い、マニュアルを整備することでヒューマンエラーを少なくしています。 このように、どちらの建築会社に依頼したとしても、それぞれの方法で現場管理しているため、同じ品質の家に住めるでしょう。 工期については工務店の方が短くなる傾向にあり、社内ルールが厳格化しているハウスメーカーは長期化する傾向にあります。 建築会社や建築時期によって工期は大きく変わるため、事前に確認することをおすすめします。 アフターサービスやメンテナンスの違い アフターサービスやメンテナンスでは、ハウスメーカーのフォロー体制が手厚いといえるでしょう。 家を建築する場合、施工主は国土交通省が定める「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、家に関する重要な部位の破損や雨漏り、シロアリ被害などについて10年間の保証を義務付けなければなりません。 そのため、どの建築会社で建築しても最低10年間は保証があるだけではなく、建築会社が独自に設定している保証やアフターサービス、メンテナンスが多くあります。 このようなアフターサービスに関するフォロー体制はハウスメーカーの方が手厚く、専門の部署を設置している会社も多くあります。 中には60年保証を掲げているハウスメーカーもあるため、工務店との大きな違いといえるでしょう。 ※参考:住宅の品質確保の促進等に関する法律|国土交通省 違いで分かるハウスメーカーのメリット・デメリット ここまで、ハウスメーカーと工務店の違いについて解説しましたが、選択するためにはメリット・デメリットも把握しておく必要があります。 そこで、この章ではまずハウスメーカーのメリット・デメリットについて解説します。 後述する、工務店のメリット・デメリットと合わせて参考にしてください。 ハウスメーカーのメリット ハウスメーカーのメリットは以下の通りです。 ネームバリューのある家に住める 長期保証と手厚いアフターサービスで安心感を得られる メンテナンスフリーの家に住める 特例(※)を最大限に活かせる ※住宅ローン控除の上限最大や、贈与税の非課税枠最大など ハウスメーカーは、認知度が高い建築会社であることが多いため、建築したことをステータスにできます。さらには、ネームバリューがあることで施工不良などのトラブルが少ない安心感にもつながります。 また、ハウスメーカーの特徴として、充実したサービスとメンテナンスフリーの外壁導入があり、安心して過ごせるでしょう。 それ以外にも、高機能住宅の建築によって住宅ローン控除の上限が最大になったり、贈与税の非課税枠を最大にしたりなどが可能です。 このように、ハウスメーカーで家を建てることで「安心」に繋がるメリットが多いといえます。 ハウスメーカーのデメリット ハウスメーカーのデメリットは、以下の通りです。 コストが工務店に比べて高くなる 細かい希望が通らないことが多い ハウスメーカー主体で打合せが進むことがお多い 工期が想定よりも長くなることがある ハウスメーカーと工務店に費用の見積りを依頼した場合、ハウスメーカーの方が高くなる傾向にあります。 特に、本体価格と地盤改良の部分に大きな価格差が生じてしまい、違和感を覚える人も少なくありません。ハウスメーカーの見積りで本体価格が高くなる理由としては、高機能なスペックと広告費が上乗せされている点です。 また、地盤改良はハウスメーカーが自社の品質を担保するために必要な費用です。このように、本体価格と地盤改良のどちらにも、自社ブランドを保つために必要な費用が含まれていることになり、コストが高い点は一概にデメリットとはいえない部分でもあります。 その他のデメリットとして、大手の会社特有の社内ルールによって軽微な設計が変更できなかったり、打ち合わせの回数が限定されたりなどがあります。 工期が工務店よりも長くなる可能性を踏まえると、ハウスメーカーのデメリットは「自由度が低い」という点に集約できるでしょう。 違いで分かる工務店のメリット・デメリット 次に、工務店のメリット・デメリットを解説していきます。 ハウスメーカーと工務店は会社の規模から施工可能エリアまで、さまざまな点が異なります。そのため、メリットとデメリットにおいても、工務店ならではのポイントが多くなるでしょう。 工務店のメリット 工務店のメリットは以下の通りです。 コストがハウスメーカーに比べて安くなる 細かい希望が通りやすくなる オリジナル性の高い家を建てられる 工期が短い 工務店のメリットは、上記を踏まえるとこだわりの家が建てられると一言で表せます。 ハウスメーカーに比べて会社の規模が小さい傾向にあり、社員数が少ない工務店は年間の着工棟数が少なくなります。その分、1回の依頼にかけられる時間は多くなり、理想の家を建てられる可能性が高くなるでしょう。 また、ハウスメーカーに比べて工期が短くなるという点も、家賃と利子の負担が少なくなるというメリットになります。 工務店のデメリット 工務店のデメリットは、以下の通りです。 品質保持やサービス面に不安がある 建築できない土地がある 担当者が変わると提案が変わることが多い ネームバリューがない 工務店はハウスメーカーと比べるとサービス面では少ない傾向にあり、メンテナンスもフリーではないケースがあります。そのため、初期コストが低くとも何十年も住むことで、トータルコストは同額になることもあるでしょう。 また、建築できる土地に制限を設けていることがあり、その内容も担当者によって変わることがあります。 このことから、工務店のデメリットは自由度が高い一方で「品質やサービスに安定感がない」という点になるでしょう。 ハウスメーカー・工務店それぞれに向いている人の特徴 この章では、ハウスメーカーと工務店のそれぞれに向いている人の特徴を解説します。 どちらのカテゴリーにもメリットとデメリットがあるため、この章で解説する人物像に近い方を選ぶことが大切です。 ハウスメーカーに向いている人 ハウスメーカーに向いている人の特徴は、以下の通りです。 「安心感」を家に求めたい人 資産価値を担保したい人 ハウスメーカーで建築する人には、大手ならではの安心感や充実したアフターサービスの魅力にメリットを感じる点が挙げられます。 また、将来売却する場合に高く売りたい人や資産価値の高い家を相続させたいなど、「投資」の観点で注文住宅を検討する場合もハウスメーカーを選ぶ傾向にあります。 工務店に向いている人 工務店に向いている人の特徴は、以下の通りです。 家のコストを抑えたい人 オリジナル性の高い家を建てたい人 工務店を選ぶ人は、コストを抑えたい人と、こだわりの詰まった家を建てたい人が非常に多いといえます。 ハウスメーカーの建材は工場で大量生産するため、どうしても同じような家になってしまいます。その点、工務店であれば自由度の高い設計ができ、コストの微調整も可能です。 このように、「コスト」と「こだわり」の両立を目指したい人には、工務店がおすすめです。 ハウスメーカーや工務店に関するよくある質問 最後に、ハウスメーカーや工務店に関するよくある質問を紹介します。 工務店で家を建てる際の注意点は? 良い工務店と悪い工務店の見分け方は? ハウスメーカー選びに疲れたらどうすればいい? 順番に回答していきます。 工務店で家を建てる際の注意点は? 工務店で家を建てる場合、担当者の対応に注意しましょう。 工務店は担当者によって提案に差が生じることがあり、場合によっては工務店の良さが伝わらないことがあります。 したがって、担当者に違和感があれば、遠慮せずに変えてもらうことをおすすめします。 良い工務店と悪い工務店の見分け方は? 工務店は、着工棟数がハウスメーカーに比べて少ないため、なるべく多く着工している工務店から検討することをおすすめします。 その上で、口コミや近所の評判を参考にして見分ける方法が有効です。 ハウスメーカー選びに疲れたらどうすればいい? ハウスメーカーの選定は短期間で何社も打合せすることになり、疲れてしまうことがあります。 その場合は、一度期間を空けて気持ちが落ち着いてから再開しましょう。 鹿児島県・宮崎県のハウスメーカーなら国分ハウジング ここまで、ハウスメーカーと工務店の違いを解説しました。どちらにも、それぞれの良さがあるので、自分のライフプランに合わせて洗濯することが重要です。 鹿児島県や宮崎県で家づくりを検討している方は、ぜひ国分ハウジングにご相談ください。 国分ハウジングは、設立35年(2023年時点)を誇る老舗のハウスメーカーです。鹿児島県での住宅着工棟数が4年連続No1で、非常に多くの支持を集めています。 また、建物プランも50種類以上取り扱っており、お客様に寄り添いながら理想の間取りを提案いたします。
-

【注文住宅】家を建てるなら土地と施工会社のどっちから決める?理由もわかりやすく解説
本記事では、家を建てる際に土地と施工会社のどちらから決めるべきかについて解説します。 注文住宅を建てるためには「土地」と「施工会社」を決める必要がありますが、どちらを優先して検討すべきか判断しかねている人は少なくありません。 土地と施工会社は、決める順番によってメリット・デメリットがあるので、それぞれを把握した上で優先順位を付けましょう。 【この記事でわかること】 ● 家づくりにおいて土地と施工会社(ハウスメーカー)どちらを先に決めるべきか ● 施工会社に土地探しを依頼した方がよいかどうか 家を建てるなら土地と施工会社(ハウスメーカー)のどちらから決める? 結論からいうと、家を建てる場合は施工会社から先に決めることが望ましいといえます。ただし、土地と施工会社のどちらを先に決めた場合でも、メリットとデメリットがあります。 土地を先に決めるメリット 土地を先に決めるデメリット 施工会社(ハウスメーカー)を先に決めるメリット 施工会社(ハウスメーカー)を先に決めるデメリット まずは、この章で解説するメリット・デメリットを押さえておきましょう。 土地を先に決めるメリット 土地を先に決めることで、勤務ルートや通学ルート、周辺のライフインフォメーション、車の駐車想定台数などをイメージした状態で建物を検討できます。 特に、駐車計画は建物のプランに大きな影響を与えることになるため、駐車台数がおおよそであっても確定している状態は大きなメリットといえるでしょう。 土地を先に決めるデメリット 土地を先に決めることで建物に充てる予算が決まってしまい、最悪の場合は建物の広さや仕様を妥協しなければならなくなります。 そのため、エリアや立地に余程のこだわりがないのであれば施工会社を決め、建物の予算と大きさが確定した状態で土地を探すことがおすすめです。 施工会社(ハウスメーカー)を先に決めるメリット 施工会社が決まれば、建物の予算と必要な建築面積も決まることになり、土地探しが進めやすくなります。 建物の大きさだけを決めて土地探しすることも可能ですが、その場合は施工会社によって予算が大きく変わってしまい、予想外の資金計画になることもあります。 たとえば、30坪の家を坪単価50万円のローコスト住宅メーカーと120万円の大手ハウスメーカーで比べた場合、建物の本体価格差だけでも2,100万円です。 このように、施工会社を決めて家づくりを進めることで、資金計画が大きく崩れるリスクがない点は大きなメリットです。 施工会社(ハウスメーカー)を先に決めるデメリット 施工会社から先に決めた場合は、施工会社の仕様や特徴に合わせた土地を探さなければなりません。 たとえば、鉄骨のユニット工法で建築する施工会社の場合、道路幅が狭かったり電線が近くにある場合などは建築できません。 また、道路によってはガードマンを設置する必要があり、他の施工会社に比べて余計な費用がかかるケースもあるでしょう。 このように、施工会社を決めることで土地以外の費用が高くなることもあるので、注意しなければなりません。 施工会社(ハウスメーカー)を先に決めるのが良い理由 ここでは、施工会社を先に決めるべき理由について解説します。 住宅ローン借入額の削減や予算オーバーを防げる デザインを自由に決められる 生活を想像しやすくなる 機能を充実させられる 後悔のない納得の家を建てるためにも、この章で解説するポイントは家づくりを始める前に押さえましょう。 住宅ローン借入額の削減や予算オーバーを防げる 施工会社を先に決めることで、建物にかける予算が確定します。その結果、総予算から建物の予算を差し引いた金額が土地の予算となり、予算内におさまる土地を重点的に捜索可能です。 また、施工会社が決まると長期優良住宅やこども未来補助の申請可否が分かるため、住宅ローンの金利優遇を受けられるかどうかが判明します。 このように、施工会社を決め建物の予算とスペックが分かることで、家づくりにかかる費用がより具体的になります。 デザインを自由に決められる 土地が決まっていない状態であれば、外観や居住スペースの間取りなどを自由に設計できます。 まずは、要望を詰め込んだ間取りを設計し、その上で優先順位を付けて土地を探しましょう。 このようなステップを踏むことで、優先順位の高い要望を確実に盛り込んだ家を建てられるだけではなく、納得度の高い注文住宅となります。 生活を想像しやすくなる 間取りや駐車計画がはっきりとした状態で土地探しを進めるので、土地を実際に見た時にリビングや玄関の位置をイメージしながら検討できます。 このようなイメージ付けは、土地探しする上で非常に重要なポイントとなります。したがって、建物の予算やおおまかな間取りを決めた上で、土地探しを始めることが重要です。 機能を充実させられる 施工会社から先に決めることで建物の仕様を十分に検討でき、機能を充実させられます。 特に、高気密・高断熱の家を建てる際には機能が重要となるため、建物に十分な時間と費用を費やしましょう。 施工会社(ハウスメーカー)に土地探しを依頼する際の注意点 施工会社は一般的に建築専門となり土地のプロではありませんが、土地探しも合わせて依頼するケースは少なくありません。 この章では、施工会社に土地探しを依頼する際の注意点を解説します。 ・そもそも土地探しに対応してくれないケースもある ・土地探しだけを依頼することはできない 順番に見ていきましょう。 そもそも土地探しに対応してくれないケースもある 施工会社は、不動産会社のように公開されている土地を全て把握していないケースもあり、本来の業務とは異なるステップになる傾向があります。 したがって、土地探しを依頼したとしても不動産会社を紹介されるケースが多いでしょう。 土地探しだけを依頼することはできない 施工会社は、一般的に土地だけを探す依頼は受けられません。 施工会社による土地探しは、あくまでも家を建てるために必要なステップとして手伝う程度であることを把握しておきましょう。 土地探しと施工会社(ハウスメーカー)に関するよくある質問 最後に、土地探しと施工会社に関するよくある質問を紹介します。 ハウスメーカーは土地探しに強いといえる? 土地が決まっていないのにハウスメーカーに依頼するのは問題ない? ハウスメーカーによる土地探しの期間はどのくらい? 順番に回答していきます。 ハウスメーカーは土地探しに強いといえる? ハウスメーカーは一般的に、土地探しが専門分野ではありません。ただし、多くの不動産会社と提携しているため、結果的に土地のプロに依頼するのと同様の情報を入手できます。 したがって、施工会社が決まった場合は不動産会社を合わせて紹介してもらい、希望の建物が建てられる土地も提案してもらいましょう。 土地が決まっていないのにハウスメーカーに依頼するのは問題ない? 土地が決まっていなくとも、ハウスメーカーに依頼することは可能です。 その場合は、建物の予算と建築面積を先に決められるため、じっくりと土地探しができます。 ハウスメーカーによる土地探しの期間はどのくらい? ハウスメーカーが最終的に土地を決めるまでは、1ヶ月前後の期間が必要となるでしょう。 ハウスメーカーに土地探しを依頼した場合は、一般的に不動産会社を紹介されることになるため、担当者にどのような土地を探しているのかを伝える必要があります。 これらの期間を踏まえると、最低でも1ヶ月程度は必要であることを押さえておきましょう。 家を建てるなら土地探しは施工会社(ハウスメーカー)に依頼しよう 予算や建物の仕様で、妥協せずに家づくりを進める場合、施工会社を先に決めることが望ましいといえます。ただし、施工会社は不動産会社と提携しているケースがほとんどであるため、土地も合わせて探してもらうことが重要です。 国分ハウジングでは、お客様に寄り添いながら最適なプランを提案いたします。土地探しに関するご相談も承りますので、ぜひ一度国分ハウジングへお問い合わせください。 来場予約|国分ハウジング
-

敷地面積とは?建築面積・延床面積との違いや制限をわかりやすく解説
注文住宅を検討する際には、敷地面積や建物面積、延床面積といった言葉をよく目にすることがあります。それぞれ建築する上で重要なポイントになるものの、建築会社から説明を受けても内容が難しく理解できていない人も少なくありません。 この記事を参考にしながら、それぞれの特徴を理解しましょう。 【この記事でわかること】 ● 敷地面積と建築面積・延床面積の違い ● 建築面積に含まれない間取りの特徴 ● 延床面積に含まれない間取りの特徴 敷地面積とは 敷地面積とは、土地全体の面積のことです。 土地の物件資料に記載されている土地面積は敷地面積となっていますが、敷地面積には「公簿面積」と「仮測量面積」、「確定測量面積」があります。 そのため、次に挙げる特徴を把握した上で物件資料に記載されている面積がどれにあたるのかを確認することが重要です。 種類 特徴 公簿面積 法務局に備え付けられている、全部事項証明書に記載されている面積 仮測量面積 土地家屋調査士が土地を測量し、所有者の承諾を得る前の面積 確定測量面積 仮測量の結果に基づいて土地所有者と周辺所有者の押印を得た状態の面積 仮測量面積は所有者の承諾を得る前の面積となり、公簿面積よりは正確な面積です。確定測量面積は、登記することで新たに公募面積となるため、最も正確な面積といえます。 敷地面積と建築面積・延床面積の違い この章では、建築面積、延床面積を解説しながら、敷地面積との違いを明確にしていきます。 それぞれ建築する上で重要な指標となるため、家づくりを始めるタイミングまでにしっかり理解しておきましょう。 建築面積とは 延床面積(建物面積)とは 順番に解説していきます。 建築面積とは 建築面積は「水平投影面積」とも呼ばれ、建物を上空から見た際の面積のことです。最も投影面積が広い階層の面積が適用されることになり、建物の面積を表すわけではありません。 建築面積は、土地に対する建築面積を制限する「建ぺい率」の計算に使用され、建ぺい率60%の地域であれば、50坪の土地に建築面積が30坪以下の家を建築できることになります。 このように、建築面積は建築する建物の面積に大きな影響を与える面積だといえるでしょう。 延床面積(建物面積)とは 延床面積は建物全体の総床面積となり、柱や壁の中心から内側にある全ての床面積を合計した面積となります。 建築面積が建ぺい率の計算に使用される一方で、延床面積は容積率の計算に使われます。 容積率は、土地面積に対しての延床面積倍率を制限した割合です。たとえば、容積率200%の地域で50坪の土地に建築する場合は、延床面積を100坪以内に設計する必要があります。 このように、前述した建築面積と合わせて建築を制限するために使用されるのが、延床面積となります。 住宅の面積に関するさまざまな制限 住宅は、建ぺい率と容積率による制限を受けることを解説しましたが、それ以外にも「高さ」に関する制限を受けることになります。 日影規制 斜線規制 接道義務 この章では、建築基準法で定められる上記3点の高さ制限について、霧島市役所が公開している『霧島市用途地域別制限一覧』のデータを参考に解説します。 日影規制 日影規制は、家が作る影に制限を設けた規制です。1年で最も日が長くなる冬至の8時〜16時(北海道の場合は8時〜15時)に生じる影が測量対象となります。 日影規制は用途地域によって規制内容が変わり、たとえば霧島市の第1種低層住居専用地域だと10m以内は4時間、10mを超える部分は2.5時間となります。 このように、家を建てることで隣地の日照に大きな影響を受けないように制限することが、日影規制の目的です。 斜線規制 斜線規制とは、道路もしくは隣地の境界に対し、ある一定の角度に建物が斜線しないよう制限した規制です。 この規制は、日光や風通りが確保できる街を維持することが目的で設けられています。 たとえば、霧島市の第1種低層住居専用地域では、道路の端面から1.25の勾配ラインを20m引き、その間に建物が来ないよう制限されることになります。 斜線規制には道路斜線や隣地斜線、北側斜線の3種類があり、どれも非常に複雑な勾配計算が必要です。したがって、無理に自分で計算せず建築会社に現地を確認してもらい、制限をクリアした建築が可能かどうかを見極めてもらいましょう。 接道義務 接道義務とは、敷地に建物を建てる場合に、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければならない決まりです。 鹿児島県には道路の接道に関して許可基準が設けられており、建築するためには4m以上の道路に2m以上設置しなければなりません。ただし、4m未満であっても規定の面積をセットバックすることで建築許可がおりるなど細かなルールがあります。 このように、道路が4m未満の土地を検討する場合は、必ず不動産会社か建築会社に現地確認してもらいましょう。 ※参考:敷地等と道路との関係規定に係る許可基準 建築面積は建ぺい率によって制限される 前述したとおり、建築面積は建ぺい率によって大きく制限されます。 建ぺい率の制限は、圧迫感のある街並みとならないための措置や、延焼のリスクを下げる効果があるため、鹿児島県以外の都道府県でも設定されています。 そのため、家づくりを検討する場合には土地や建物だけでなく、規制されている法令についても調べることが重要です。 建築面積はバルコニーやひさしは含まれるのか 結論からいうと、バルコニーやひさしは建築面積に含まれません。 建築面積は上空から測定した面積となるものの、バルコニーやひさしは建築部位として算出しないのが原則です。 ただし、2mを超えるバルコニーや屋根があり部屋の内部に設置するインナーバルコニーなどは、建築面積に含まれる部分があるため注意が必要です。 延床面積に含まれない箇所 この章では、延床面積に含まれない箇所を解説します。 出窓 ベランダ・バルコニー 吹き抜け ロフト 外部階段 延床面積が小さくなると容積率の条件をクリアしやすくなり、建物の固定税も低くできます。 この章で解説する各箇所のポイントを押さえ、最適な延床面積を目指しましょう。 出窓 出窓は、家の外に向かって出っ張ったような設計の窓を指し、窓の下部にスペースがあり小物などを飾れます。 出窓は、延床面積を減らしつつ家屋内のスペースを増やすためによく使われる間取りです。 奥行きが50cm未満、床からの高さが30cm以上、床から1.35mの高さに半分以上の窓があるなど、細かい規定があることを押さえておきましょう。 ベランダ・バルコニー ベランダやバルコニーは、2m以内まで延床面積から除外できます。 ただし、2mを超えたベランダやバルコニーは全て延床面積となるわけではなく、超えた部分のみ除外となることを把握しましょう。 それ以外にも、格子を取り付けると延床面積に含まれるなど、市区町村が独自に設定しているルールもあるため、間取り採用時には注意が必要です。 吹き抜け 吹き抜けは床自体がないため、延床面積には含まれません。 開放的な空間の演出と採光を多く取り入れられるため、玄関などに導入するケースが多くあります。ただし、吹き抜けの2階は床がなく部屋として利用できないため、部屋の広さを十分に確保できる間取りを意識しましょう。 ロフト ロフトは、デッドスペースを有効活用するために導入される間取りで、部屋を効率良く使用したい人に人気です。 ロフトはあくまでも「部屋」ではないため、延床面積に含めず設計できる一方で、さまざまな制限があります。 制限内容は市区町村によって異なる部分が多いため、必ず建築会社に問い合わせて、制限内容を確実に確認した上で検討しましょう。 外部階段 二世帯住宅などで設置される外部階段は、いかなる形状、角度であっても延床面積に含まれません。したがって、延べ床面積を計算する際には、まず外部階段を除外し計算しましょう。 敷地面積・建築面積・延床面積に関するよくある質問 最後に、敷地面積・建築面積・延床面積に関するよくある質問を紹介します。 マイホームの一般的な広さはどのくらい? 駐車場を設ける場合に敷地面積はどれくらい必要? 敷地面積・建物面積・延床面積の平均はどれくらい? マイホームの一般的な広さはどのくらい? 『住宅金融支援機構』のデータによると、全国と首都圏では123.8㎡、近畿圏は127.1㎡、東海圏は123.5㎡、そのほかの地域では123.1㎡が平均的な広さです。 なお、鹿児島県の平均は107.6㎡となっています。 ※参考:2021年度集計表|住宅金融支援機構 駐車場を設ける場合に敷地面積はどれくらい必要? 『一般財団法人自動車検査登録情報協会』で定められる車両サイズにもとづき、スーパーマーケットや、ショッピングモールに設置されている駐車場は、2.5×5mのサイズであることがほとんどです。 ただし、並列に並べた場合は少々圧迫感があるため、「3m×6m=18㎡」を駐車場用地として検討することをおすすめします。 ※参考:自動車の種類|一般財団法人 自動車検査登録情報協会 敷地面積・建物面積・延床面積の平均はどれくらい? 建物面積と延床面積は前述した通りとなり、敷地面積は中央値を平均とした場合に全国および首都圏、近畿圏で100㎡〜110㎡が平均となりました。 また、それ以外のエリアとして東海圏では160〜170㎡、そのほかの地域では230〜240㎡が平均値となっており、鹿児島県の平均においても同様の230〜240㎡となります。 敷地面積・建物面積・延床面積の特徴や違いを理解しよう 敷地面積と建物面積、延床面積は家づくりにおいてそれぞれが重要なポイントとなっており、理解したほうがよい面積といえるでしょう。 そのため、それぞれの面積は家づくりをスタートする前に、しっかりと押さえておくことをおすすめします。 国分ハウジングでは、鹿児島県に特化した建築プランを提案しております。土地を最大限に有効活用した家を建てたい人は、ぜひ国分ハウジングまでお問い合わせください。 来場予約|国分ハウジング
-

建売住宅と注文住宅の違いとは?メリット・デメリットや価格差の違いを比較
この記事では、建売住宅と注文住宅の違いや、メリット・デメリットを解説します。 マイホームを検討する際に、注文住宅と建売住宅どちらにすべきか迷う人は少なくありません。初めての家づくりでは、何をポイントに決めたら良いのかわからないことも多々あります。 建売住宅と注文住宅をさまざまな観点から比較することで、どちらを選ぶべきかの方向性が見えてくるでしょう。 【この記事でわかること】 ● 建売住宅と注文住宅の違い ● 建売住宅のメリット・デメリット ● 注文住宅のメリット・デメリット ● 建売住宅と注文住宅の価格差 ● 建売住宅と注文住宅のどちらを選ぶべきか? 建売住宅と注文住宅の違い まずは、建売住宅と注文住宅の特徴を把握して、違いを明確にしましょう。 建売住宅とは? 注文住宅とは? 順番に解説していきます。 建売住宅とは 建売住宅とは、土地と建物がセットになっていて、設計や仕様もすでに決まった状態で販売されている住宅のことです。 すでに完成済の物件が多く、事前に建物をチェックできるのが特徴です。完成前の物件であっても設計や仕様がほとんど確定しており、軽微な変更以外はできません。 入居スケジュールも立てやすく、初めての方にもわかりやすい住宅です。 注文住宅とは 注文住宅とは、何も決まっていない状態から設計事務所や工務店、ハウスメーカーなどに依頼し、最初から計画する住宅のことです。 メーカーや工務店によって、ある程度の企画やグレードが決まっていて、基本のパターンから自分好みにアレンジしていく場合もあります。 建売住宅のメリット ここでは、建売住宅のメリットについて解説していきます。 入居までの期間が短い 価格が安い傾向にある 実物を確認してから購入できる 順番に見ていきましょう。 入居までの期間が短い 建売住宅のメリットの1つとして、注文住宅に比べて入居までの期間が短い点が挙げられます。 建売住宅は、完成品が売りに出されることが一般的であるため、注文住宅に必要な検討期間、確認申請期間、工事期間などが不要です。 建売住宅の場合も購入を検討する期間は必要ですが、決断して住宅ローンの手当てを受けられれば、即入居も可能といえるでしょう。 建売住宅と注文住宅の入居までの期間の差は、約6ヶ月〜1年程度となります。 価格が安い傾向にある 建売住宅には、注文住宅よりも価格が安くなりやすいメリットがあります。 価格が安い理由として、以下の5点が挙げられます。 部材や設備をまとめて購入できるため、原価ダウンが可能 工期が短い分、コストが低くなる 計画やプランの打ち合わせがないので、人件費や固定費の削減につながる 売主売買になるケースがほとんどであり、仲介手数料などが不要 完成品を購入するため、設計費や工事管理費が不要、もしくは安く抑えられる 建築コストを低く抑えられることは、マイホームを購入する人にとっても検討しやすい材料になるでしょう。 実物を確認してから購入できる 実物を見て購入するかどうか決められることも、建売住宅の大きなメリットです。 専門家ではない限り、図面を見ただけで建物の実態や詳細を理解することはできません。一方で、建売住宅は実物を見て購入するか否かを決められるので、購入者にとっては大きなメリットといえます。 建売住宅のデメリット 建売住宅はメリットだけではなく、デメリットも把握しましょう。 建築の過程を確認できない 隣家との距離が近い 間取りや設備の仕様が決まっている 順番に解説していきます。 建築の過程を確認できない ほとんどの建売住宅が完成品のため、購入検討者は土地の状況や工事の過程を確認できません。 購入検討者にとっては、一生ものとなるマイホームのため、建築前の土地状況や建築中の建物状況は確認したいところです。 可能であれば、地耐力調査結果や施工中の検査状況、施工写真などを確認させてもらいましょう。 隣家との距離が近い 建売住宅の中でも、特に分譲住宅で見受けられるデメリットの1つとして、隣家との距離が近い点が挙げられます。 分譲住宅は、限られた土地の中になるべく効率的に多くの住宅を建てようとするので、どうしても隣家との距離が近くなりがちです。 とはいえ、建築基準法で最低限の採光距離は決められているので、ある程度は光が入るでしょう。 間取りや設備の仕様が決まっている 建売住宅は、ほとんどの場合に完成品として販売するため、間取りや設備を自由に選べません。 また、未完成物件であっても変更できる間取りや設備には限度があり、家自体の構造や大掛かりな間取り変更には対応できません。 注文住宅のメリット ここでは、注文住宅のメリットを解説していきます。 建築の過程を確認できる 資産としての価値が高い 設計の自由度が高い 順番に見ていきましょう。 建築の過程を確認できる 注文住宅は最初から建てるので、施工前の土地状況や施工中の建物状況を逐一チェックできます。参考までに、以下のチェックポイントを紹介します。 土地における地耐力の調査結果 地中内埋設物や地下水位の確認など 基礎工事終了時 建て方終了時 建物完成時 他にも、施工中に気になる点があったら施工業者に確認して説明を求めましょう。 資産としての価値が高い 注文住宅は、ユーザーのこだわりにより高級素材を利用したり、凝った間取りにしたりする場合が多いので、建売住宅に比べて資産価値が高くなる傾向にあります。 ただし、経年劣化による資産性の低下は注文住宅でも避けられないので、定期的なメンテナンスは必要です。 設計の自由度が高い 注文住宅の醍醐味ともいえるメリットが、自分が思い描いた通りの理想的な家づくりができる自由度の高さです。 構造的に受ける制約以外は、自分たちが望むほとんどの要望は実現できるでしょう。 予算的に上限値を決めておかないと、夢を実現したいあまり当初の資金計画に狂いが生じかねないので、取り入れたい設備や仕様は優先順位を付けるようにしてください。 注文住宅のデメリット 注文住宅においても、メリットだけではなくデメリットが存在します。 入居までの期間が長い コストが割高になる 完成をイメージしにくい 順番に見ていきましょう。 入居までの期間が長い 注文住宅の場合、計画をスタートしてから入居するまでの期間が建売住宅に比べて長いデメリットがあります。 注文住宅の場合、検討を始めてから入居まで通常1年3ヶ月程度、検討や土地探しに時間を要すると2年近くかかることも少なくありません。 完成している住宅が気に入って、住宅ローン審査さえ通過できればすぐに入居できる建売住宅とは、期間の差がかなりあります。 コストが割高になる 注文住宅は、素材や仕様について1つずつこだわりを持って決めるケースが多いので、総体的に建築コストは高くなります。 ただし、その分で資産価値は建売住宅よりも高くなることが多いので、長期的に見れば損はないといえるでしょう。 完成をイメージしにくい 住まいの専門家でない限り、一般のユーザーが図面や仕様書だけで完成をイメージすることは困難でしょう。 現在は、3DパースやVRによる疑似体験などで事前にイメージを確認できる場合もありますが、建売住宅のように現物を確認することはできません。 建売住宅と注文住宅を価格差の違いで比較 ここでは、建売住宅・注文住宅の価格差をチェックしておきましょう。 それぞれの価格差で、押さえておきたいポイントは以下の通りです。 家づくりにかかる費用の違い メンテナンスやランニングコストの違い 固定資産税などの税金の違い 順番に見ていきましょう。 家づくりにかかる費用の違い ここでは、鹿児島県・全国平均・東京都における建売住宅と注文住宅の価格を比較しました。 建売住宅 注文住宅 合計 土地代金 建物代金 鹿児島県 3,050万7,000円 3,560万1,000円 778万4,000円 2,781万7,000円 全国平均 3,604万9,000円 4,455万5,000円 1,444万9,000円 3,010万6,000円 東京都 4,826万4,000円 6,104万8,000円 3,413万5,000円 2,691万3,000円 ※参考:2021年度フラット35利用調査|住宅金融支援機構 鹿児島県においては、土地付き注文住宅価格は建売住宅価格の約1.17倍、全国平均では1.24倍、東京都においては1.26倍の結果となりました。 鹿児島県の場合、全国平均や東京都に比べて購入費総額に占める土地代の比率が低いので、建売・注文いずれの住宅も建てやすいといえます。 この結果から、土地付き注文住宅は建売住宅のおよそ2割増と考えて良いでしょう。土地を所有していれば、いずれの地域でも注文住宅の方が建売住宅よりも安くなります。 メンテナンス費用やランニングコストの違い 同じ素材を使用していれば、メンテナンス費用やランニングコストは基本的に変わりません。 一般的に、注文住宅の場合は自然素材が採用されることも多いので、メンテナンス費用やランニングコストが高くなりがちです。 逆に、手間のかかりにくい素材を選べば、メンテナンス費用やランニングコストを抑えられます。 建売住宅は、汎用性の高い標準的な素材を使用している場合が多く、建売住宅と注文住宅のどちらが手間ひま要らずかは、使用している素材によります。 固定資産税などの税金の違い 固定資産税などの税金も、どちらが安いかについては一概に言えません。ただし、高級素材を使用したグレードの高い注文住宅の場合は、固定資産税が高くなる可能性があります。 注文住宅の場合、計画したマイホームが認定長期優良住宅に該当すれば、固定資産税の軽減措置が受けられる可能性があります。 建売住宅と注文住宅どっちがいい? 建売住宅が良いか、注文住宅が良いかは人それぞれであるため、どちらが良いと特定できるものではありません。 ただし、それぞれに適した条件を有している場合はあります。 建売住宅が向いている人 注文住宅が向いている人 順番に解説していきます。 建売住宅が向いている人 建売住宅が向いている人の条件は、以下の4点です。 土地は所有していないが、予算をなるべく低く抑えたい人 なるべく早く入居したい人 デザインや仕様に深いこだわりのない人 決めるなら実物を見て決めたい人 上記を踏まえると、建売住宅は特に、スピーディかつ低価格で購入を検討したい人に向いているといえます。 注文住宅が向いている人 注文住宅が向いている人の条件は、以下の4点です。 土地を所有している人 デザインや間取りに自分なりのこだわりがある人 建物完成に時間をかけられる人 予算的にある程度の余裕が持てる人 注文住宅を建てる場合でも、土地の有無によって建物にかけられる予算は変わるので、あくまで目安としてください。 ライフスタイルに合わせて建売住宅か注文住宅か決めよう 建売住宅にするか注文住宅にするかは、個人のライフスタイルや家づくりの考え方によります。 暮らし方や間取り、素材などに強いこだわりがあれば、注文住宅となり、土地も購入して予算を抑えたい場合は建売住宅となるでしょう。 ポイントは、自分たちの暮らし方に合わせて、実現したい要望に優先順位を付けておくことです。仮に理想的な家が完成しても、住宅ローンの負担が増えるような資金計画は望ましくありません。 家づくりにおいては、暮らす人のゆとりあるあたたかい暮らしを実現することが重要です。したがって、広い視野を持ちながら、理想的なマイホームを選びましょう。 国分ハウジングは、お客様に寄り添いながら高品質の家づくりを提案しています。土地探しやプランニング、資金計画など、住まいに関するお悩みやご相談がありましたら、ぜひ一度国分ハウジングのモデルルームにお越しください。 来場予約|【公式】国分ハウジング|鹿児島・宮崎のハウスメーカー
-

長期譲渡所得とは?短期との違いや税額の計算方法・特例をわかりやすく解説
この記事では、長期譲渡所得や税額の計算方法などを解説していきます。 所有している不動産を売却する場合、購入したときの価格よりも高く売れた場合は利益に対して税金が発生します。この利益を譲渡所得と呼び、所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得の2種類があります。 この記事では、譲渡所得にかかる税金の計算方法や特例に加えて節税方法も解説するので、所有不動産の売却を考えている人はぜひ最後までお読みください。 【この記事でわかること】 ● 長期譲渡所得とは? ● 長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い ● 長期譲渡所得の計算方法 ● 長期譲渡所得の特例 長期譲渡所得とは? 長期譲渡所得とは、マイホームや土地を売却して発生した譲渡所得のうち、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地や建物を売却したときの利益です。 売却した日から5年を経過しただけでは、長期譲渡所得にならない点に注意しましょう。 長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い 長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いは、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が異なる点にあります。 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年間を超えている場合の譲渡所得です。また、短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下の譲渡所得です。 所有期間が異なることによって、税率も大きく変わってきます。 以下で、税率と期間についてポイントをまとめています。 長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率一覧 長期譲渡所得と短期譲渡所得の期間 1つずつ解説していきます。 長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率一覧 長期譲渡所得と短期譲渡所得では、発生した利益に対して課税される税率が大きく違います。 まずは、それぞれの税率を把握してください。 <譲渡所得税の税率> 長期譲渡所得税率 短期譲渡所得税率 20.315% 39.63% 短期譲渡所得は、長期譲渡所得の倍近い税率であることを認識しましょう。そのため、不動産売却のタイミングを間違えると、大きな損失が生まれてしまいます。 次に、譲渡所得税の中身を見ていきましょう。譲渡所得税は「所得税(復興特別所得税を含む)+住民税」で構成されます。 長期譲渡所得 短期譲渡所得 所得税(復興特別税含む) 15.315% 30.63% 住民税 5% 9% 計 20.315% 39.63% ※参考:長期譲渡所得の税額の計算|国税庁 ※参考:短期譲渡所得の税額の計算|国税庁 復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するために創設された税金です。平成25年から令和19年までの間、全ての納税者に課税されます。 復興特別所得税の税額は、基準所得税額の2.1%です。 長期譲渡所得と短期譲渡所得の期間 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年間を超えている場合の譲渡所得のことをいいます。 短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下の譲渡所得です。 例えば、取得日が2018年2月1日、売却日が2023年2月13日の場合を考えます。この場合、所有期間は5年を超えているため、長期譲渡所得のように見えますが、2023年1月1日時点では5年を超えていないので、実際は短期譲渡所得となります。 つまり、2024年1月1日以降でないと長期譲渡所得になりません。このように、誤って申告すると税率が倍近く異なるので注意しましょう。 長期譲渡所得の計算方法 ここでは、長期譲渡所得の税額の計算方法を見ていきましょう。計算式は以下の通りです。 税額={譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除}×税率 譲渡価額は不動産を売った金額のことです。売却した金額から、費用として控除できる項目があります。 取得費 譲渡費用 特別控除 上記の項目を控除して得た金額に税率を掛けて税額を求めます。 取得費 取得費とは、土地や建物を取得するためにかかった費用のことです。土地の場合は購入価格、建物の場合は購入代金、または建築代金から減価償却費相当額を差し引いた金額です。 取得費を求める計算式は、以下の通りです。 取得費=土地購入代金+(建物代金−減価償却費相当額) 減価償却費相当額を求める計算式は以下の通りです。 減価償却費相当額=建物取得価額×0.9×償却率×経過年数 償却率は建物構造や使用用途が事業用か非事業用かによって異なります。売却したい建物の構造や事業用か否かはチェックしましょう。 マイホームは非事業用建物に分類されます。構造ごとに決められている非事業用建物の償却率は以下の通りです。 <非事業用建物の償却率> 建物の構造 償却率(%) 木造 0.031 木造(モルタル) 0.034 (鉄骨)鉄筋コンクリート造 0.015 鉄骨造(鉄骨の厚み3mm以下) 0.036 鉄骨造(鉄骨の厚み3mm超〜4mm 0.025 経過年数は、6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満の端数は切り捨てて計算します。 譲渡費用 譲渡費用とは、不動産を売却するときに発生する費用のことで、具体的には以下が該当します。 仲介手数料(売買時に不動産業者に支払う手数料) 印紙代(売買契約書) 測量費用(売買のため確定測量をした場合) 解体費用(建物を解体して土地だけ売却する場合) 上記の費用も、長期譲渡所得にかかる税額を低減してくれます。 特別控除 特別控除は、土地や建物を売却するときに一定の要件をクリアすれば、譲渡価額から一定額を差し引いてくれる控除です。 いずれも高額の控除のため、自分の売買に適用されるか否かを以下で十分に確かめましょう。 長期譲渡所得の特例が利用できるケース ここでは、前述した長期譲渡所得の特例(特別控除)を見ていきます。 紹介する特例は、以下の4つです。 特定居住用財産の買換え特例 10年超所有軽減税率の特例 居住用財産の3,000万円特別控除 空き家の3,000万円特別控除 1つずつ解説します。 特定居住用財産の買換え特例 居住用財産であるマイホームを令和5年12月31日までに売却して新たにマイホームを買ったとき、一定要件を満たせば特例を利用できます。 特例は、買い換えたマイホームを将来売却するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べられるものです。ただし、最初の売却時の譲渡税は非課税になるわけではなく、買い換えたマイホームを将来売却するときに上乗せして課税されることに注意しましょう。 特例を受けられる適用要件は、以下の通りです。 自分が居住している家屋であること 現在居住していない場合は、居住しなくなった日から3年を経過する日が属する3月31日までに売却すること 売却した人の居住期間が10年以上で、かつ売却した年の1月1日において売却した建物や土地の所有期間が10年を超えること 買い換える建物の床面積が50㎡以上で、かつ買い換える土地の面積が500㎡以下であること マイホームを売却する年の前年から翌年までの3年の間に買い換えること 売却した年から過去3年以内に、以下の特例を受けていないこと マイホームを売却したときの3,000万円の特例 マイホームを売却したときの軽減税率の特例 マイホームの譲渡損失について損益通算・繰越控除の特例 収用・土地区画整理などの特例 売却したマイホーム、買い換えたマイホームとも国内にあること 売却代金が1億円以下であること 買い換えるマイホームが令和6年1月1日以後の入居かつ新築の住宅で、以下の2点いずれにも該当しない場合には一定の省エネ基準(※)を満たすこと 令和5年12月31日以前に建築確認を受けている 令和6年6月30日以前に建築されている 親子や夫婦など親類関係のある人に対する売却でないこと ※:断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上であることを指す ※参考:特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁 上記の要件を満たすかチェックし、必要に応じて特例を利用しましょう。 10年超所有軽減税率の特例 10年超所有軽減税率の特例は、自分が居住していたマイホームを売却したときに、その不動産を10年超で所有していれば税率を軽減してくれるものです。 10年超所有軽減税率の特例が持つ最大のメリットは、居住用財産の3,000万円の特例と併用できることです。 以下の表で軽減される税率を確認しましょう。 <10年超所有軽減税率> 譲渡所得が6,000万円以下 譲渡所得が6,000万円超 6,000万円以下の部分 6,000万円超の部分 所得税(復興特別税含む) 10.21% 10.21% 15.315% 住民税 4% 4% 5% 計 14.21% 14.21% 20.315% ※参考:国税庁|マイホームを売ったときの軽減税率の特例 譲渡所得が6,000万円以下の場合、税率が6%以上軽減されるため、忘れず利用しましょう。 居住用財産の3,000万円特別控除 居住用財産の3,000万円特別控除とは、マイホームを売却したときに、所有期間の長さに関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度のことです。 この特例が受けられる要件は以下の通りです。 自分が居住している家屋であること・現在居住していない場合は、居住しなくなった日から3年を経過する日が属する12月31日までに売却すること 売却した年の前年、前々年にこの特例、またはマイホームの譲渡損失について損益通算や繰越控除の特例を受けていないこと 売却した年、その前年、及び前々年にマイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと 売却した家屋や土地について、収用や区画整理による特別控除の特例を受けていないこと 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地に住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却すること 親子や夫婦など親類関係のある人に対する売却でないこと ※参考:マイホームを売ったときの特例|国税庁 控除額が大きいため、特例が受けられるかどうかを十分に確認しましょう。 空き家の3,000万円特別控除 空き家の3,000万円特別控除とは、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋(空き家)またはその敷地を期間内に売却する場合に、所定の金額を控除できる制度です。 対象となる売却の期間は平成28年4月1日から令和5年12月31日までです。譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除されます。 控除されるためには、下記の要件を満たす必要があります。 昭和56年5月31日以前に建築されたこと 区分所有建物登記がされていないこと 相続の開始直前において被相続人以外に居住していた人がいないこと 相続または遺贈により家屋(空き家)と敷地を取得したこと 相続の開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却すること 売却代金が1億円以下であること 売却した家屋や敷地について、相続財産を譲渡した場合の特例や収用などの特例を受けていないこと 親子や夫婦など親類関係のある人に対する売却でないこと ※参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 特例の適用要件が煩雑であるため、事前に税務署や税理士に特例が受けられるか否かを確認すると良いでしょう。 長期譲渡所得にかかる税額をシミュレーション ここでは、長期譲渡所得税にかかる税額をシミュレーションしていきます。 3,000万円の特別控除が適用できる場合とできない場合をシミュレーションします。設定する条件は以下の通りです。 【条件1:譲渡価額など】 ● 取得日:2018年2月1日 ● 売却日:2024年1月15日(購入後15年経過) ● 譲渡価額:6,000万円 ● 取得費:3,744万5,000円 ● 譲渡費用:500万円 【条件2:売却物件の購入時期・価格など】 ● 土地価格:2,000万円 ● 建物価格:3,000万円 ● 建物構造:木造 税額の計算式を整理します。 減価償却費相当額 建物取得価額×0.9×償却率×経過年数 取得費 土地購入代金+(建物代金−減価償却費相当額) 長期譲渡所得税額 {譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除}×税率 この計算式より、減価償却費相当額と取得費は以下の通りです。 減価償却費相当額 3,000万円×0.9×0.031(木造償却率)×15年=1255万5,000円 取得費 2,000万円+(3,000万円−1,255万5,000円)=3,744万5,000円 続いて、長期譲渡所得税額を、3,000万円の特別控除が適用できる場合とそうでない場合について整理します。 <3,000万円の特別控除が適用できる場合> 長期譲渡所得税額 {6,000万円−(3,744万5,000円+500万円)−3,000万円}×20.315%=0円 3,000万円控除があるため、課税譲渡所得金額が0円になり譲渡所得税は課税されません。 <3,000万円の特別控除が適用できない場合> 長期譲渡所得税額 {6,000万円−(3,744万5,000円+500万円)−0円}×20.315%=356万6,298円 納付税額は100円未満切り捨てで計算されるので、356万6,200円です。 3,000万円の特別控除の有無によって、納税額が350万円以上も異なります。 したがって、利用できる特別控除はぜひ利用しましょう。 長期譲渡所得に関するよくある質問 長期譲渡所得についてよくある質問は以下の通りです。 譲渡所得や特別控除の確定申告は不要? 相続した土地を3年以内に売却すると節税になる? 譲渡所得の基礎控除って何? それぞれ回答していきます。 譲渡所得や特別控除の確定申告は不要? マイホームを売却して譲渡所得が発生する場合(売却益が発生する場合)は、確定申告が必要です。 逆に、譲渡損失が発生した場合(売却損が発生する場合)は、納税額はゼロになり確定申告は不要です。 ただし、納税額がゼロであっても、特例を適用した場合には確定申告が必要になるので忘れず申告しましょう。 相続した土地を3年以内に売却すると節税になる? 相続した土地を3年以内に売却すれば、相続税の取得費加算の特例が適用できて節税になります。 この特例は、譲渡所得税を計算する際に譲渡価額から控除される取得費に相続税の一部を上乗せできる制度です。 相続した不動産3年以内の売買の場合には、ぜひ利用しましょう。 譲渡所得の基礎控除ってなに? 所得税の課税所得金額を計算する場合、全ての人の所得金額から48万円の基礎控除が認められています。 すなわち、譲渡所得などの金額が48万円以下の場合、税金は課税されず確定申告の必要もありません。 長期譲渡所得や短期譲渡所得の仕組みを理解して適切な判断を 不動産を売却すると売却益が発生しますが、売却した不動産の所有期間に応じてその売却益に対して譲渡所得税が発生します。 譲渡所得税の税率は5年以内の短期譲渡所得のほうが高く、投資目的で購入した不動産をすぐ売却する場合、40%近い税率が適用されてしまいます。 5年を超える長期譲渡所得の場合でも20%を超える税率が適用されるので、この記事で紹介した特例や特別控除を活用して節税しましょう。 国分ハウジングでは、お客様に寄り添いながら最適なプランを提案いたします。土地探しやプランニング、資金計画など住まいに関するお悩みやご相談がありましたら、ぜひ一度国分ハウジングの住宅展示場やモデルルームにお越しください。 来場予約|【公式】国分ハウジング|鹿児島・宮崎のハウスメーカー
-

新築と中古物件のリノベーションはどちらがおすすめ?メリット・デメリットで比較
自分のマイホームを持ちたいと思った時に、新築物件と中古物件のどちらが良いかで迷われている人も多いのではないでしょうか。 新築物件と中古物件とも、コスト面や建物の状況だけでなく利便性や周辺環境なども含めてメリット・デメリットがあります。 新築、中古それぞれについて、重要なポイントを把握しておけば、自分にとって理想的なマイホームを手に入れやすくなるでしょう。 この記事では、新築物件と中古物件のメリット・デメリットを比較しながら、どちらを選べば良いか、判断材料を紹介します。 【この記事でわかること】 ● リノベーションとはなにか ● 新築・リノベーションのメリット・デメリット ● 新築と中古物件のリノベーションをコスト面で比較 ● 新築と中古物件のリノベーションそれぞれに向いている人の特徴 そもそもリノベーションとは? リノベーションとは、新しく住む人のライフスタイルや価値観に合わせて間取りや内装、設備など全てをゼロから考え直し、作り替えることです。 間取りを、現代の暮らしに合わせて変更できるだけではなく、機能面でオール電化や高断熱仕様を採用するなど、新たな価値を創造できることがリノベーションの醍醐味といえます。 リノベーションは、古くなった部分を改修して原状回復する「リフォーム」とは根本的に異なることを理解しておきましょう。 新築と中古物件のリノベーションはどちらがおすすめ? 「新築と中古のリノベーションのどちらが良いか?」の回答に対しては、一概にどちらが良いと言い切ることはできません。なぜなら、購入する人が理想とする暮らしやライフプランによって、どちらが適しているかは異なるからです。 例えば、予算を抑えて新しい生活をしたい人であればリフォームが適していて、他人が住んだ家に抵抗がある人は新築が望ましいでしょう。 自分にとって一番優先したいことは何かを見極めて、どちらが良いか選ぶようにしましょう。 新築のメリット ここでは、新築ならではのメリットについて解説していきます。 間取りや構造を自由に設計できる 新築の設備や機材が整っている 耐震性や省エネ性能が優れている 保険や税制優遇が充実している 上記4点について、順番に見ていきましょう。 間取りや構造を自由に設計できる 新築の注文住宅であれば、予算の範囲内で思い通りの構造や間取りを設計しながら、マイホームを建てられます。 建築法規の範囲内であれば、平屋や3階建てなども実現できるでしょう。 中古物件の場合、室内は自由に変更できても構造や階数の変更は容易にできません。 新築の設備や機材が整っている 新築の住宅の大きなメリットは、最新設備が整っている点にあります。 太陽光発電システムやLED照明、高効率エアコンなど最新設備を自由に選べるでしょう。 耐震性や省エネ性能が優れている 新築と中古物件の大きな違いは、高耐久性や高気密・高断熱性、省エネ性などです。 新築では、中古と違って新技術を取り入れた建材が使用できます。 したがって、新築では地震などの自然災害に強く、夏は涼しくて冬は暖かいだけではなく、光熱費を抑えた暮らしができるでしょう。 保険や税制優遇が充実している 新築住宅では、条件によってさまざまな税制優遇を受けられる点がメリットです。 住宅ローン控除や固定資産税・都市計画税、さらには不動産取得税、印紙税などにおいても優遇措置が設けられています。 住宅ローン控除は借入から13年間、住宅ローン年末残高の0.7%分を所得税・住民税から控除できます。 一方で、築25年(木造の場合20年)を超えた中古住宅の場合、一定以上の耐震性能を有している物件でなければ、住宅ローン控除は受けられません。 新築のデメリット 新築には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。 条件次第ではコストが割高 完成までをイメージしづらい 工期が長い傾向にある ここからは、上記3点のデメリットを見ていきましょう。 条件次第ではコストが割高 中古物件が、その時点での市場価格や供給状況を見て価格決定されるのに比べて、新築物件は割高になるケースが多いといえます。 なぜなら、新築の物件は機能や新しい設備を有することに加えて、売却するための広告宣伝費やモデルルーム代などの経費が建築費に含まれるからです。 新築物件を購入後すぐに売却しようとすると、購入価格から10〜20%程度安くなってしまうのは、こうした理由があると理解しておきましょう。 完成までをイメージしづらい 新築の注文住宅は現物を確認できないため、仕上がりの詳細がわかりません。 現在は、3DパースやVRを利用しているケースもあり、ある程度は事前確認が可能です。 しかし、中古物件と比べると細かい仕様まで正確にチェックすることは困難といえます。 したがって、同等の部材や設備を採用している実際の着工中現場を見せてもらったり、モデルルームで見本を確認したりすることで、完成イメージに近づけていきましょう。 工期が長い傾向にある 新築注文住宅は、土地探しから完成まで1〜1年3ヶ月程度の時間が必要です。 土地がなかなか見つからなかったりプラン決定に手間取ったりすると、1年半以上の期間を要することもあると認識しておいた方が良いでしょう。 中古物件をリノベーションするメリット 中古物件のリノベーションには、新築と異なるメリットが存在します。 条件次第では予算を削減できる 完成までのイメージをしやすい 立地条件の選択肢が広がる 順番に見ていきましょう。 条件次第では予算を削減できる 中古物件のリノベーションは、新築に比べて予算をかなり低く抑えられます。 設備が旧式である点や、内装自体が経年劣化している点は否めませんが、現代では外装も含めたフルリノベーションも可能です。 予算を抑えた上で、新築と同じように快適な生活空間が得られるでしょう。 完成までのイメージをしやすい 中古物件のリノベーションは、現物を確認できて完成をイメージしやすい点もメリットです。 どの柱や壁を残さなければならないかなども自分の目で確認できるので、生活動線などもイメージしやすいでしょう。 立地条件の選択肢が広がる 中古物件のリノベーションは、新築に比べて総予算を低く抑えられるため、その分立地の選択肢が広くなります。 新築の場合には高額となり手の届かない駅付近の利便施設や、学校などの諸施設が揃っている物件などを検討できる可能性も高くなるでしょう。 中古物件をリノベーションするデメリット 新築同様に、中古物件のデメリットも解説します。 理想の間取りを実現できないケースがある 設備や機材が古く補修工事が発生しやすい 災害時の耐久性に不安が残る 上記は、主に中古物件そのもののデメリットと捉えましょう。 したがって、これらをリノベーションでどこまで改善できるかが重要です。 理想の間取りを実現できないケースがある リノベーションにおいては、必ずしも自分が理想とする間取りを実現できないケースがあると押さえておきましょう。 1970〜80年代に主流の間取りは、現代において生活動線など使いづらい点が多く見られます。また、築30年近くの物件になると、木造や軽量鉄骨造では法定耐用年数を経過しているため、構造的な劣化や価値の減少は否めません。 このように、築年数が極端に古い物件は構造的に変更ができないケースがあるため、リノベーションでどこまで改善できるのか事前に把握しておく必要があるでしょう。 設備や機材が古く補修工事が発生しやすい 設備や機材が古いことで、補修工事が発生しやすい点は、中古物件およびリノベーションのデメリットといえるでしょう。 仮にリノベーションが完了した場合でも、新築に比べて設備や機材などの故障リスクが高く、リノベーション後に修繕コストがかかるケースがあります。 また、リノベーション時に交換できない設備や機材もあるので、購入を検討する段階で建築会社などに確認しましょう。 災害時の耐久性に不安が残る 中古物件の場合、新築と比べると耐久性や耐震性などの構造に不安が残ります。これらは、リノベーションで容易に改善できるとはいえないため、デメリットの1つです。 特に、1981年(昭和56年)6月以前の旧耐震基準に基づいて建築された物件は、築年数も40年以上になるため、どうしても検討する場合は内容に注意しなければなりません。なお、木造住宅の場合は2000年6月1日以降(※)、新基準が適用されているのでチェックしましょう。 ※2023年1月現在で築23年のケース 物件の現物を見られるのであれば、なるべく設計士や建築会社の担当に耐久性を確認することをおすすめします。 新築と中古物件のリノベーションをコスト面で比較 新築と中古物件をリノベーションする場合のコストについて、「2021年度フラット35利用者調査」などを参考に比較してみましょう。 なお、諸費用は新築、中古物件ともに土地・建物代金における合計の10%と仮定します。 【購入物件の平均面積など】(※1) 新築(土地付注文住宅) 中古戸建 土地面積 198.5㎡(60.04坪) 164.3㎡(49.7坪) 住宅面積 111.4㎡(33.69坪) 113.1㎡(34.2坪) ※参考:2021年度フラット35利用者調査|住宅金融支援機構 【購入総コスト目安の比較】 新築:土地付注文住宅 中古戸建 土地・建物購入費(※2) 4,455万円 2,614万円 諸費用(土地建物の10%) 445万5,000円 261万4,000円 リノベーション費用(※3) – 349万7,000円 合計 4,900万円5,000円 3,225万1,000円 ※参考1:2021年度フラット35利用者調査|住宅金融支援機構 ※参考2:2021年度住宅リフォームに関する消費者実態調査|一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 購入する土地面積や、住宅面積に多少の差異はありますが、新築物件は中古物件の1.5倍以上のコストが掛かっているとわかりました。 新築とリノベーションが向いている人の特徴 ここまで、新築と中古物件のリノベーションをさまざまな点から比較してきましたが、どちらが良いかについては、人それぞれの部分もあり一概にはいえません。 新築が向いている人 中古物件のリノベーションが向いている人 ここでは、どちらが良いか悪いかではなく、それぞれがどのような人に向いているかを解説していきます。 新築が向いている人 設備や機能を最新のもので揃えたい人は、新築物件がおすすめです。 中古物件でも最新の設備は導入できますが、構造上引き継ぎができない場合もあります。 また、災害などに備えて耐震性や耐候性にこだわりたい場合も、新築物件のほうが対応しやすいでしょう。 中古物件のリノベーションが向いている人 予算を低く抑えたい人は、中古物件がおすすめです。 低い予算の範囲内でも新築より立地条件の良い物件を選択でき、将来的な資産価値の目減り率は緩やかになるでしょう。 住宅ローンが短いこともメリットの一つで、その分買い替えもしやすくなる利点があります。 新築とリノベーションは理想とするライフスタイルで判断しよう 「新築か中古物件のリノベーションか」の選択に、絶対的な答えはありません。 なぜなら、購入する人の状況によって、どちらを選択すれば良いか分かれるからです。 例えば、転勤が多い人や将来買い替えをしたい人にとっては、中古物件が適していて、終の住処として考える人は新築が適しているといえるでしょう。 このように、自分の理想とする家づくりに照らし合わせて、選択してください。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
-

注文住宅の打ち合わせの回数・期間は?流れや内容・コツも徹底解説
注文住宅を建てる際に大切なことは、建築会社との打ち合わせをしっかり実施することです。 自分たちの希望や不安を建築会社に正確に伝えるところからスタートしましょう。 何も決まっていない状態であるため、建築会社と打ち合わせを重ねて共通認識を持つことから理想の家づくりは始まります。 この記事では、建築会社と打ち合わせする回数や流れ、ポイントについて解説します。 【この記事でわかること】 ● 注文住宅を計画する際の打ち合わせ回数や期間 ● 注文住宅を計画する際の打ち合わせの流れ ● 建築会社との打ち合わせで決める内容 ● 打ち合わせを有意義なものにするコツ 注文住宅における打ち合わせの回数や期間 打ち合わせの回数や期間は、建主の要望や建築会社の方針によってさまざまです。 一般的な打ち合わせの回数や期間 打ち合わせの回数が変動する理由 打ち合わせの回数が多いのは問題? ここでは、上記3点について見ていきましょう。 一般的な打ち合わせの回数や期間 注文住宅における打ち合わせの回数は、白紙の状態から完成するまでの間に10〜20回程度が一般的です。 着工前のプランや資金の打ち合わせが10〜15回、着工後から竣工までの式典や色決め、現場の立ち会いなどで3〜5回程度、引渡し前で2〜3回程度が目安となるでしょう。 計画を決定するまでに、週に1度打ち合わせをしていくと仮定したら、3ヶ月程度かかることになります。 トータルして考えると、最初の打ち合わせから引渡しまで、約1年3ヶ月の期間が必要です。 打ち合わせの回数が変動する理由 打ち合わせの回数が変動する最も大きな理由は、プランがなかなか決まらないからです。 こだわりの多い人の場合、プランの打ち合わせが20回以上におよぶ場合もあります。 また、打ち合わせに参加する人が途中で変わるとプランに対する要望も変更になり、打ち合わせの回数が増えてしまうこともあるでしょう。 打ち合わせの回数が多いのは問題? 建築会社は建主の要望通りの家づくりができない状況は避けたいので、お互いのイメージが共有できるまで打ち合わせすることは非常に大切だと考えています。 その意味では、打ち合わせの回数が多いことに問題はありませんが、打ち合わせごとに決定すべき内容を決めて無駄のない打ち合わせができるように心掛けましょう。 注文住宅における打ち合わせの流れ 打ち合わせの大きな流れは、主に以下3つに分けると整理しやすいでしょう。 着工前の流れ 着工後(建築中)の流れ 引渡し前の流れ ここからは、それぞれの段階で必要になる打ち合わせ内容や注意すべき点を解説していきます。 着工前の流れ 着工前の打ち合わせは、プランと金額を決めるためのものです。 主な流れや、一般的な打ち合わせの回数は以下の通りです。 要望・予算のヒアリングと計画の現地調査の承諾(1回) 現地調査結果に基づいてゾーニング・配置プランなどの打ち合わせ(1〜3回) 要望に基づいて間取りプランの打ち合わせ〜プラン決定(3〜5回) モデルルームや展示場を参考に住宅設備や大まかな色などを決定(2〜3回) 決まったプランや設備をもとに見積書を作成し金額打ち合わせ〜金額決定(2〜3回) 建築請負契約及び住宅ローン手続き準備の打ち合わせ(1回) 着工前のプラン・金額を確定する打ち合わせ回数は、概ね10〜15回程度になるでしょう。 着工後(建築中)の流れ 着工から引渡し前までの打ち合わせ内容は、現場の施工状況の確認と細かい色決めや設備・仕様について品番まで決めることです。 設備や色は契約前にほぼ決まっているものの、建築会社はこの段階でメーカーや設備業者に発注するために、建主と仕様や色について再確認の打ち合わせをしなければなりません。 また、着工時の地鎮祭や上棟時の式典などの打ち合わせも実施するので、この段階での打ち合わせ回数は3〜5回になるでしょう。 引渡し前の流れ 引渡し前は、現場の最終確認と最終時金の支払いや登記手続きなどについて打ち合わせします。施工状況に問題がなければ、建築会社から正式に引渡しを受けて引越しの準備をします。 打ち合わせの回数は2〜3回程度になるでしょう。 注文住宅の打ち合わせで決める内容 打ち合わせをスムーズに進めるためには、事前に決めておいた自分のこだわりや予算を建築会社の担当者に正確に伝えることが大切です。 資金計画 建物に関する内容 ショールームやモデルハウスに足を運ぶ スケジュール計画 ここでは、打ち合わせで決めるべき内容について説明します。 資金計画 資金計画は大切な打ち合わせ項目の1つです。 資金計画に関して打ち合わせする際は、事前に自分が月々支払える金額と頭金の額を明確に把握しておきましょう。 月々の支払額から、支払い総額や借入上限額を打ち合わせすることが可能になり、その結果建築に充てられる予算額を検討しやすくなります。 概算の予算額を把握できたら、住宅ローンの事前相談を申し込みましょう。金融機関は、自分で探すだけではなく、建築会社からも紹介してもらうことをおすすめします。 なぜなら、借入れ条件などで有利になる可能性があるからです。 建物に関する内容 建物の内容を決めることが、建築会社との打ち合わせではメインです。 決めるべき項目は以下の3点です。 構造:木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など 階数:平屋、2階建て、3階建てなど 間取り:生活動線など 住宅を建てる場合、木造や鉄骨造が人気です。 建築会社は、構造によって得手不得手があるので打ち合わせ時に確認しましょう。 階数は、第一種住居専用地域のように高さ10mまでしか建てられない場合もあるので、3階建ての計画が難しい場合もあります。 間取りは、事前に部屋数、洋室・和室の数、取り入れたい生活動線などを事前に決めておきましょう。 ショールームやモデルハウスに足を運ぶ 設備機器を決めるときは、なるべく実物を見て決めることをおすすめします。 キッチンの高さや照明の照度、給湯の使いやすさなどは日々の生活に直接影響する部分のため、ショールームやモデルハウスで確認しましょう。 スケジュール計画 建物の計画、予算が確定したらスケジュール計画を決めましょう。 建築会社と確認申請許可予定日・着工予定日を確認したら、地鎮祭、着工の日程を決めます。 建物が完成するには、一般的に4ヶ月くらいの期間が必要になるので、自分たちの都合や引越しのタイミングを考えて着工時期を調整します。 注文住宅における打ち合わせのコツ 理想の家づくりを実現するために、知っておきたい打ち合わせ時のコツを紹介します。 予算を明確にする 優先順位を明確にする スケジュールに余裕を持たせる 記録を取りながら疑問や不安を確実に解消させる 納得できるまで打ち合わせの機会を設ける 上記4点について、順番に解説していきます。 予算を明確にする 月々に支払える金額から建物の予算を決めたら、予算の範囲内に抑える意志を持ちましょう。 理想のマイホームを求めるあまり、予算以上のオプションなどを選びたくなる人も少なくありません。しかし、どうしても必要な項目でない限り、予算内に抑えるようにしてください。 明確な上限値を設定することで、打ち合わせもスムーズに進みます。 優先順位を明確にする 注文住宅の打ち合わせ時は、優先順位を明確にすることも忘れてはいけません。 予算に明確な上限値を設定しても、ショールームなどで話を進めていくうちにオプション追加などの影響で、予算オーバーになることがよくあります。 家づくりを専門にしている人ではない限り、予算を決める段階で細かいオプションまで意識することは困難といえるため、無理もありません。 したがって、このような事態を避けるためには、事前に優先順位を決めておきましょう。予算オーバーした場合は、優先順位の低い項目からカットして、なるべく予算内に収めましょう。 スケジュールに余裕を持たせる 建物が完成するまでのスケジュールを決めることは大切なことであり、スケジュール通りに実行することも重要です。 しかし、完成するまでの間には台風などの災害や、近年蔓延している新型コロナウイルスによる部材の搬入遅れなど、さまざまな障害が起こるおそれもあります。 したがって、不測の事態にも備えられるように、スケジュールには2〜3ヶ月程度の余裕を持っておきましょう。 記録を取りながら疑問や不安を確実に解消させる 注文住宅を建てる際には、「打ち合わせ時にお願いした仕様になっていない」などの行き違いや、言った・言わないなどによるトラブルの懸念があります。 こうしたトラブルを避けるために、以下の手順を踏みましょう。 打ち合わせ記録を残す 打ち合わせが終了した際に読み合わせして内容を確認する 打ち合わせによる記録の確認が終わった際に署名もしくは捺印する 打ち合わせにおける記録のコピーを残してお互いに認識をすり合わせる 次回以降の打ち合わせも、前回の打ち合わせ記録を確認するところから始めると、ミスのないスムーズな打ち合わせができるでしょう。 納得できるまで打ち合わせの機会を設ける 打ち合わせは、疑問点や不明点を残して終了してはいけません。基本的に、疑問に思った点はその打ち合わせの中で解消しましょう。 疑問点を解消するために調査が必要な場合は、打ち合わせ内容を記録に残し、次回の打ち合わせ時に解答をもらうことが望ましいでしょう。 疑問点や不明点を残したままで着工することは避けるようにしてください。 注文住宅の打ち合わせに関するよくある質問 注文住宅の打ち合わせでよくある質問をまとめます。 注文住宅の打ち合わせに疲れたらどうすればいい? 注文住宅の打ち合わせが進まない場合はどうすればいい? 注文住宅の打ち合わせが進まない場合はどうすればいい? 上記3点のよくある質問について、順番に回答していきます。 注文住宅の打ち合わせに疲れたらどうすればいい? なかなか思い通りにプランが仕上がらなかったり予算オーバーしたりなど、対処策が見つからないような場合に、疲れを感じることがあります。 こうした理由で疲れを感じたときは、一旦家づくりの打ち合わせから離れてみましょう。 自分がリラックスできる空間を整え、気分転換したほうが良い家づくりにつながります。 注文住宅の打ち合わせが進まない場合はどうすればいい? 打ち合わせが進まず、停滞している原因を探ってみましょう。 「自分の要望を出しても、なかなか希望通りのプランを用意してくれない」や「夫婦で意見が合わずまとまらない」など、何かしらの原因があるはずです。 原因が明確になれば、自分だけで悩まずに建築会社の担当者にも共有して、具体的に解決策を探っていきましょう。 その際は、優先順位をつけて妥協できるところは取りやめるなど、柔軟に対応してください。 注文住宅の打ち合わせは何回が理想? 結論、注文住宅の打ち合わせに制限や理想はありません。 計画や着手から完成まで10〜15回程度の打ち合わせで進むケースがあれば、20回以上の打ち合わせが必要なケースもあるでしょう。 ただし、大切なことは打ち合わせ回数を減らすことではなく、毎回の打ち合わせに疑問点や不明点を残さないことです。 自分の要望が担当者としっかり共有できるまで打ち合わせを繰り返すことが重要です。 注文住宅の打ち合わせは注意点を押さえておこう 最後に、注文住宅の打ち合わせに関して、ストレスなく進めていくポイントをまとめました。 ● 打ち合わせの前に自分の要望をしっかりとまとめておく ● まとめた要望は正確に伝え、打ち合わせした内容はその都度記録を取る ● 予算は上限を決めて、その範囲内に抑える ● 絶対に譲れない点と妥協できる点を見極めておく 以上、4点をポイントに打ち合わせを進めてみてください。それでも打ち合わせに疲れを感じたら、気分転換に一旦休みを設けましょう。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
-

人気上昇中の平屋! 新築で平屋を建てる場合のメリットやデメリットとは?
マイホームを建てるとき、平屋を検討する方は少なくありません。 一般的な2階建てや3階建ての住宅に比べて、1階部分のみでできている平屋住宅は、「階段の上り下りが不要で使いやすい」というイメージから高い人気を集めています。 ただし、実際に平屋を建てようとする場合は平屋の持つメリットとデメリットを把握しておくことが重要です。 そこで本記事では、平屋のメリットとデメリットについて、建てる際に失敗しないためのポイントも押さえながら詳しく解説していきます。 【この記事でわかること】 ● 平屋とは何か ● 平家のメリット・デメリット ● 平屋を建てる際に失敗しないためのポイント そもそも平屋とは? まずは、平屋の定義を理解しておきましょう。 平屋とは、家の中に階段を設けない1階建ての住宅のことです。リビングやその他の居室、浴室やトイレなどの水回りスペースなどがすべてワンフロアとなっています。 このように、マンションの一室を一戸建て住宅で再現したようなイメージになるでしょう。 平屋が人気の理由 平屋は、新築住宅を建てる際によく検討される人気の高い住宅といえますが、平屋が人気を集めているのにはさまざまな理由があります。 大きな理由の1つは、見た目がコンパクトでおしゃれという点です。一般的な2階建てなどの住宅に比べ、個性的でデザイン性が高く見えることで、平屋に憧れを持つケースは少なくありません。 ほかにも、ワンフロアで家事がしやすそうな点や階段がなく子育てしながら安心して暮らしやすい点なども人気の理由として挙げられます。 平家のメリット5選 平屋のメリットは、以下の通り5つあります。 コミュニケーションが取りやすい 生活動線が効率的 メンテナンス費用を削減できる 構造が安定的 バリアフリーの対応がしやすい それぞれのメリットについて、詳しい内容を見ていきましょう。 コミュニケーションが取りやすい 平屋で生活することで、家族とのコミュニケーションが取りやすいというメリットがあります。 平屋は、すべての空間がワンフロアにまとまっていることから、自然に家の中で家族と顔を合わせる機会が増え、コミュニケーションが豊かになります。 例えば、自分の部屋を持った子どもと距離が生じることを心配する親にとって、階段による隔たりが無いという点は、平屋ならではの嬉しいポイントです。 生活動線が効率的 平屋は、生活動線が効率的であるという点も大きなメリットです。 例えば、一般的な2階建て住宅の場合、1階の洗濯機から重たい洗濯物を持って2階のベランダまで運ばなければならないケースが多くありますが、平屋ならそういった手間が省けます。 子育て世帯や共働きで忙しい家庭は特に、平屋のメリットとして生活動線が効率的になるという点を押さえておきましょう。 メンテナンス費用を削減できる 平屋は、建物のメンテナンスを必要とする部分の面積が少ないことから、メンテナンス費用を削減できるというメリットもあります。 特に、外壁のメンテナンス費用は一般的に高額になりがちですが、平屋にすることで大幅に費用を抑えることが可能です。 長く住み続けることを考える際の重要なメリットとして、頭に入れておきましょう。 構造が安定的 2階建て以上の住宅に比べて、平屋は構造が安定的で地震などの災害に強いという点も、メリットとして押さえておきましょう。 1階部分のみで完成される平屋は、建物そのものの高さが低いため、地震の揺れによる影響を受けにくくなります。また、外からの風の影響を受ける面積も小さくなることから、台風などの災害にも強いといえるでしょう。 バリアフリーの対応がしやすい 家の中に階段を設けない平屋は、バリアフリーの対応がしやすいというメリットもあります。 すべての空間をワンフロアにできるので、階段や段差を無くしたバリアフリーの生活を実現することが可能です。 介護の必要がある家庭はもちろん、将来自らの老後の生活を考慮すると、バリアフリーの対応がしやすい平屋は非常に魅力的であるといえます。 平家のデメリット5選 平屋を検討する際は、メリットだけでなく以下5つのデメリットも把握しましょう。 広大な敷地が必要 防犯面で不安が残る 日当たりや風通しに注意が必要 建築費用が高い 浸水被害を受けやすい それぞれ、詳しく解説していきます。 広大な敷地が必要 平屋を建てる場合、広大な敷地が必要となるため、土地探しが大変になる可能性があります。 通常であれば、2階建て住宅に取り入れる空間をすべてワンフロアに盛り込むためには、それ相応の広さの土地を確保しなければなりません。土地面積が広くなれば、その分で土地の購入費用や、固定資産税も高くなる点を理解しましょう。 防犯面で不安が残る 平屋は1階部分のみでできているため、防犯面で不安が残るというデメリットも挙げられます。 2階以上の部屋であれば、夜間に窓を開けたままにしておくケースもありますが、平屋の場合は外からの侵入の危険を考えると不安が残ってしまいます。 平屋を建てる場合は、防犯についても検討しておくことが大切です。 日当たりや風通しに注意が必要 平屋は、周辺環境によっては日当たりや風通しに注意が必要であるという点も把握しておきましょう。 例えば、周辺に2階建て以上の建物が多くある中で平屋を建てる場合、周りの建物により日当たりや風通しが遮られてしまう可能性があります。 平屋を検討する場合は、近隣の建物の状況も必ず確認しておきましょう。 建築費用が高い 平屋を建てる場合、建築費用が比較的高くなるというデメリットもあるので注意しましょう。 平屋を検討する人の中には、階数が少ないほうが建築費用も安く済むというイメージを持っている人が多いかもしれません。しかし、実際には平屋のほうが建物の基礎工事が必要な部分が多くなり、建築費用が高額になるケースがあるので注意が必要です。 浸水被害を受けやすい 建物全体が1階部分である平屋は、浸水被害を受けやすいというデメリットもあります。 例えば、2階建て住宅の場合は大雨などによる浸水被害を受けたとき、2階に一旦避難して安全を確保することが可能です。 しかし、平屋の場合には家全体が浸水してしまい、上の階へ避難できません。したがって、平屋を検討する場合はハザードマップなどを参考に、浸水の危険性を事前に確認しましょう。 新築で平屋を建てる際に失敗しないためのポイント 新築で平屋を建てる際に失敗しないためには、以下3つのポイントを押さえておきましょう。 土地の形や向きを確認する 価格の安さだけで判断しない ライフプランの変化を考慮する 1つずつ詳しく解説していきます。 土地の形や向きを確認する 平屋を建てる場合、土地の形や向きを事前によく確認しましょう。 平屋は、建物の高さが周りよりも低くなる場合が多いため、土地の形や向きが日当たりや風通しに大きく影響します。 土地の形や向きを確認せずに平屋を建てた場合、快適な暮らしが実現できない可能性があるので注意が必要です。 価格の安さだけで判断しない 平屋を建てるとき、価格の安さだけで判断することは避けましょう。 価格の安さだけを重視して平屋を建てると、防犯できないなど入居してから後悔することになりかねません。 したがって、平屋ならではの特徴をしっかりと把握したうえで、必要な部分には費用をかけることが重要なポイントです。 ライフプランの変化を考慮する 平屋を建てる場合、ライフプランの変化を考慮することが非常に大切です。 例えば、将来子どもが成長したとき、お互いのプライバシーを守れる構造になっているかどうかを考慮することは重要なポイントとなります。 2階建て住宅に比べ、すべての部屋が同じフロアとなる平屋では、プライバシーの確保が難しくなりがちのため、将来のライフプランの変化を見据えた家づくりを心がけましょう。 平家のメリット・デメリットを把握して理想の住宅を建てよう 平屋を検討する場合は、平屋ならではのメリットやデメリットをよく理解することが非常に大切です。したがって、メリット・デメリットを把握し、理想の住宅を手に入れましょう。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/